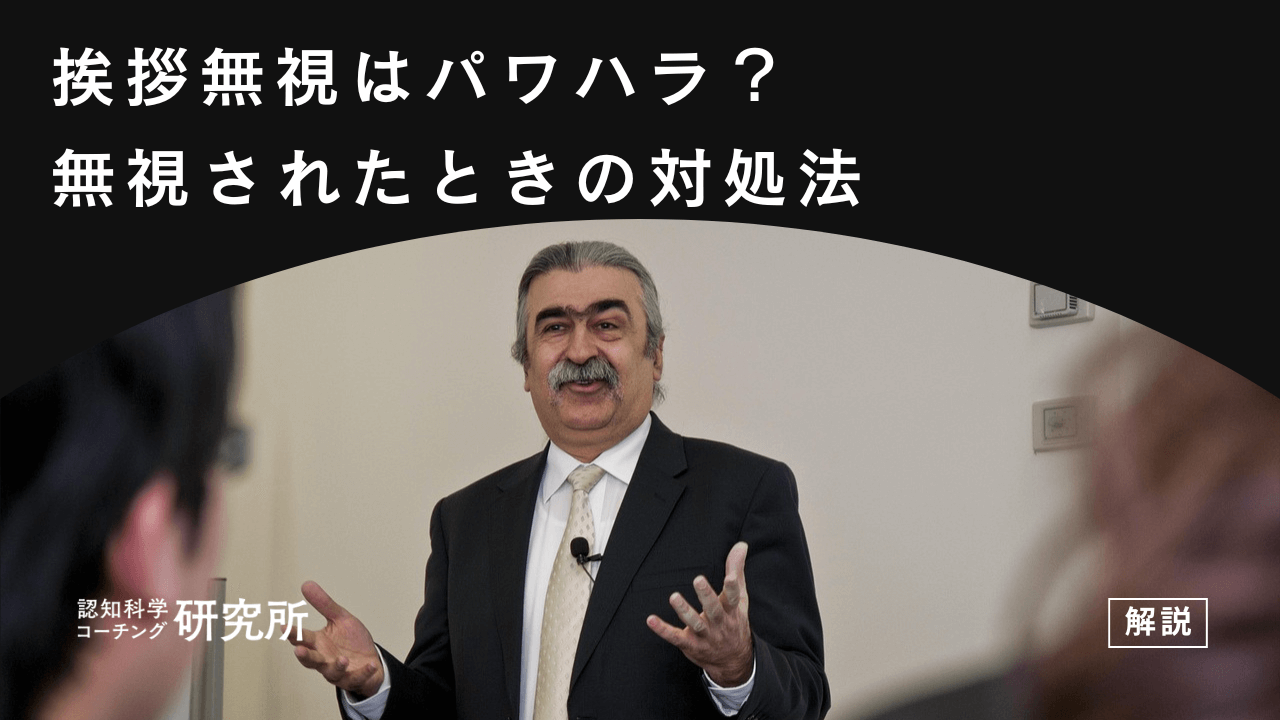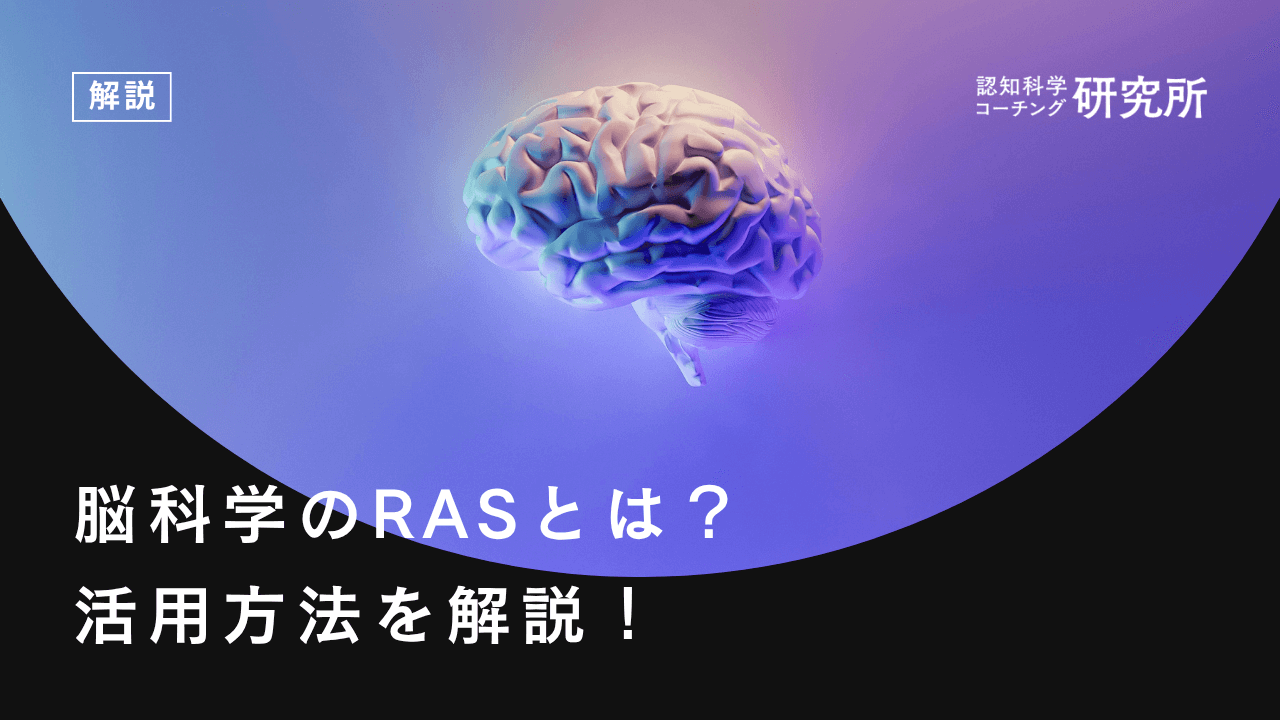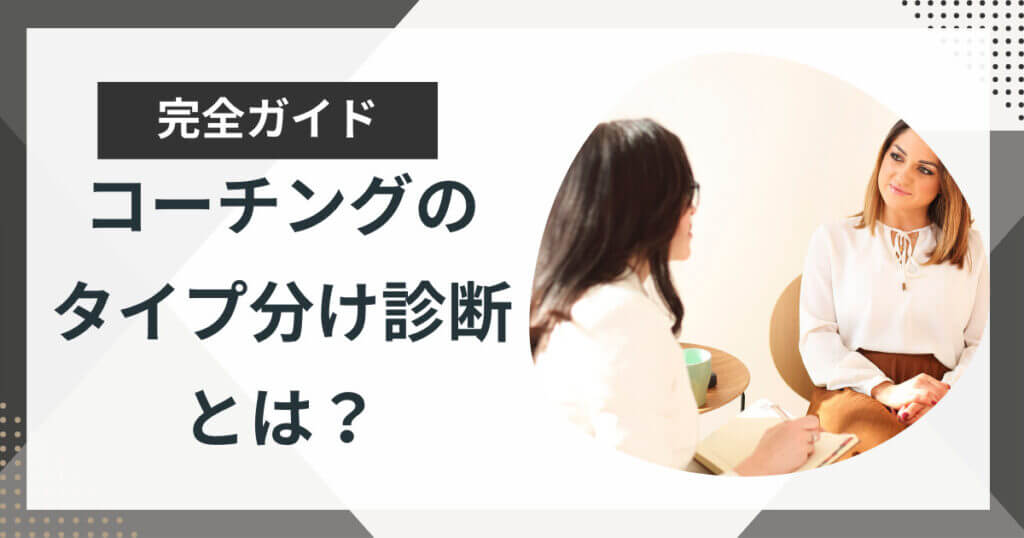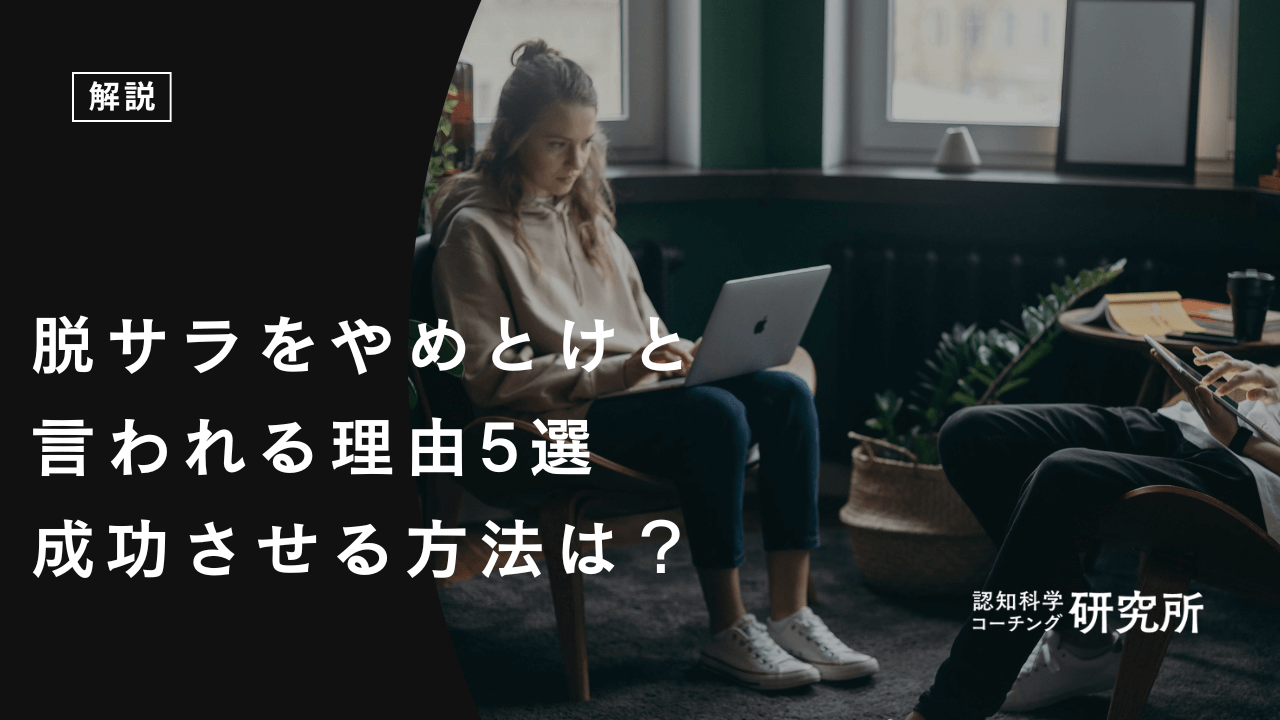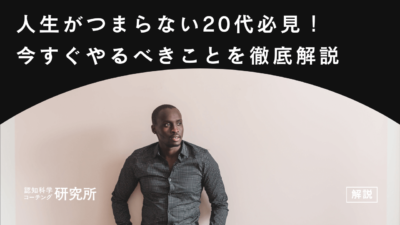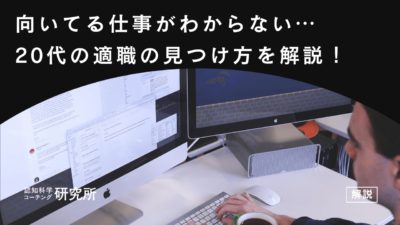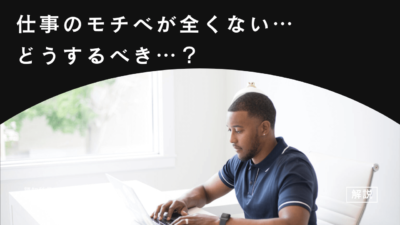脱サラがやめとけと言われる理由は?
脱サラへの不安を解消するには?
脱サラをやめとけと言われたらどうすれば良いかについて、わかりやすく解説します。
「脱サラがやめとけと言われるのはなぜ?」
「脱サラが失敗しやすいって本当?」
「脱サラするときは何を意識すれば良い?」
現代社会は、仕事への向き合い方が変化している時代。
「一つの会社で長く勤める」が当たり前ではなくなってきました。
そこで選択肢の1つのなるのが「脱サラ」
 ミズカラくん
ミズカラくん起業や独立を意識している人もいるでしょう。
しかし、脱サラしたいと考えると、反対にあうケースも多いのが現状。
特に、家族からの反対はよくあります。
脱サラは不安定さがあるので、やめとけと言われるのです。
この記事では、脱サラがやめとけと言われる理由を解説。
最後まで読めば、脱サラのリスクを理解し、自分のキャリアをしっかりと考えられるはずです。
脱サラがやめとけと言われるのは、成果が出せるかわからないから。
強みを見つけて活かすことで、脱サラ後も成果を残すことができます。
強みを見つけるワークシートを使って、成果を出せる強みを見つけ出しましょう。
脱サラとは

脱サラとは、会社員が会社を辞め、独立することです。
 ミズカラくん
ミズカラくん脱サラリーマンの略で、脱サラと言います。
例えば、会社員を辞めてフリーランスになる場合。
あるいは、会社員を辞めて、自分で会社を始めるなどの場合。
このようなケースのことを、脱サラと呼びます。
脱サラを成功させるためのポイントは、強みを活かせる仕事をすることです。
自分の得意分野で勝負した方が、成果が出やすくなります。
自分の強みが分からない場合は、ワークシートで探してみましょう。
強みを見つけられるワークシートをプレゼントするので、ぜひ使ってみてください。
脱サラして起業する成功率
脱サラして起業する成功率をデータから見てみましょう。
中小企業庁によると、創業から企業が存続している割合は以下の通りです。
| 創業1年後 | 95.3% |
| 創業2年後 | 91.5% |
| 創業3年後 | 88.1% |
| 創業4年後 | 84.8% |
| 創業5年後 | 81.7% |
5年後でも5社に4社は残っており、成功率は高いといえます。
しかし、個人事業主の場合は成功率が変わるので気をつけましょう。
 ミズカラくん
ミズカラくん個人事業主の場合、1年で約4割が廃業。
3年で約6割が廃業とも言われています。
10年生き残るのは、1割のみ。
独立に踏み切れないと悩むなら、しっかりと考えて行動した方が良いでしょう。
脱サラを「やめとけ」と言われる5つの理由

脱サラを「やめとけ」と言われる理由は、以下の通りです。
- 収入がなくなるリスクがあるから
- スキル不足で失敗する場合があるから
- 競合他社や市場が厳しいからト
- プレッシャーや不安を感じやすいから
- 初期投資がかかるケースもあるから
収入がなくなるリスクがあるから
脱サラをやめとけと言われるのは、安定収入がなくなるからです。
 ミズカラくん
ミズカラくん会社員のようにはいきません。
脱サラしてから、売上が安定するまで時間がかかる場合も多くあります。
その間の生活費をどう確保するかは、脱サラの大きな課題です。
特に、家賃やローン、家族の生活費など固定支出がある場合。
 ミズカラくん
ミズカラくん収入ゼロの期間は大きな負担になるでしょう。
準備資金や副業経験なしで飛び込むと、生活が立ち行かなくなるリスクも。
安定した収入源を複数確保してからの行動が、安全な脱サラの第一歩です。
スキル不足で失敗する場合があるから
スキル不足で脱サラに失敗する場合もあります。
 ミズカラくん
ミズカラくん会社員の経験が、そのまま通用するとは限りません。
脱サラ後は、営業、集客、マーケティングなど、幅広いスキルが求められます。
スキル不足のまま始めると、思ったように売上が伸びないでしょう。
頑張っても、事業が継続できないケースもあります。
特に、顧客獲得や集客の仕組みを作れないと、安定経営は難しいのです。
スキルに不安を感じるあなたにおすすめなのが、ワークシートを使うこと。
ワークシートを使って、自分の強みを見つけ出しましょう。
強みを活かすことで、自然と仕事で成果を出せるように。
下記の特設ページでワークシートをプレゼントするので、ぜひ使ってください。
競合他社や市場が厳しいから
競合他社や市場の厳しさも、脱サラの課題です。
 ミズカラくん
ミズカラくんどんなビジネスにも競合が存在します。
たとえば、飲食店やネットショップの場合。
参入障壁が低い一方、廃業率も高い業界です。
既存企業と差別化できないと、短期間で撤退に追い込まれるでしょう。
脱サラする場合は、市場分析と差別化できる戦略が大事。
事前の準備をしっかりと行うことで、競争に勝てる可能性が高まります。
プレッシャーや不安を感じやすいから
プレッシャーや不安も、脱サラを続けにくい理由です。
 ミズカラくん
ミズカラくん環境が合わない人もいます。
脱サラ後は、自分が動かなければ収入はゼロです。
顧客対応、資金繰り、売上確保など、すべての責任が自分にのしかかります。
このプレッシャーは、大きな負担になるでしょう。
特に収入が不安定な時期は、不安から冷静な判断ができないかもしれません。
ストレス耐性や自己管理能力がないと、長期的な事業運営は難しいといえます。
初期投資がかかるケースもあるから
業種によっては、設備費や広告費などの初期投資が必要です。
 ミズカラくん
ミズカラくん投資を回収できるかが勝負になります。
たとえば、飲食業なら開業費用が数百万円以上かかるのが一般的です。
設備費はもちろん、店舗の賃料などもかかるからです。
この費用を回収するまでに時間がかかり、資金が尽きるリスクもあります。
資金計画が甘いまま始めると、赤字が続き、廃業につながります。
開業前には、自己資金と運転資金の確保、回収計画が欠かせません。
脱サラをやめとけと言われて失敗する人の特徴4選

脱サラをやめとけと言われて失敗する人の特徴は以下の通りです。
- 計画なく脱サラを行う
- 資金管理ができずに廃業する
- 実務経験がなく成果が出ない
- 人脈やサポートがなく孤立する
計画なく脱サラを行う
計画なく脱サラを行う人は、失敗しやすいでしょう。
 ミズカラくん
ミズカラくんすぐに資金が尽きます…
たとえば、「カフェを開きたい」という思いだけで始めた場合。
立地や客単価の計算が甘ければ、赤字は必至です。
成功している人は、開業前に半年〜1年以上の準備期間を取っています。
勢いだけで会社を辞め、ビジネスプランを持たない人は高確率で失敗します。
成功には、計画を立てることが欠かせないのです。
資金管理ができずに廃業する
資金管理の影響で廃業するのもよくあるケースです。
 ミズカラくん
ミズカラくん適切な管理が欠かせません。
脱サラ後は、収入が不安定な状況になります。
日々の経費、税金、運転資金、把握すべき資金はたくさんです。
売上が出た月に、生活費や贅沢に使いすぎて失敗するケースも。
固定費を抑え、少なくとも半年〜1年分の生活費を確保してから始めるべきです。
実務経験がなく成果が出ない
チャレンジした業種の実務経験がなく、失敗するケースもあります。
 ミズカラくん
ミズカラくん想定外の課題に直面しがちです。
たとえば、Web制作で独立したいと思った場合。
制作ができても、顧客との契約や見積もりが分からなければ信頼を得られません。
やりたいことだけで、独立できるわけではないのです。
また、集客方法や業界特有のルールを知らずに苦戦することも。
副業やアルバイトで経験を積み、スキルと実務感覚を身につけてからが安全です。
人脈やサポートがなく孤立する
サポートがない場合も、失敗しやすいといえます。
 ミズカラくん
ミズカラくん人脈はとても大切です。
脱サラで多いのが、相談できる仲間や支援者がいないケース。
困ったときに助けてくれる人がいないと、問題が長期化します。
知識や経験を持った人がいると、支えになるもの。
脱サラ前に、人脈を作っておくことも大切です。
脱サラをやめとけと言われても成功する人の特徴4選

脱サラをやめとけと言われても成功する人の特徴は、以下の通りです。
- 副業をして経験を積んでいる
- 市場分析を事前に行っている
- 半年分以上の生活費を用意している
- 失敗するリスクを想定している
副業をして経験を積んでいる
いきなり独立せず、副業で経験を積んでいる人は成功しやすいです。
 ミズカラくん
ミズカラくん小さな仕事から始めてみましょう。
例えば、Webデザインでの起業を目指したい場合。
副業で仕事を受けることで、実務スキルと営業力を同時に磨けます。
実際に顧客対応や集客を経験することで、改善点が明確になるでしょう。
準備期間があることで、脱サラ後もスムーズに収益化できます。
まずは副業から、小さく始めるのは大事です。
市場分析を事前に行っている
成功する人は、事業を始める前に市場分析を行っています。
 ミズカラくん
ミズカラくん分析をして、計画を練っているのです。
たとえば、カフェを開こうと考える場合。
市場分析を行い、他店との差別化ポイントを明確にしてから開業します。
以下のようなポイントを徹底的に調べるでしょう。
- 競合の強み・弱み
- 顧客のニーズ
- 価格帯の傾向
この分析がないと、価格競争や集客難に陥るリスクが高まります。
事前に分析を行い、どうやって勝負するかを考えているのです。
半年分以上の生活費を用意している
脱サラに成功する人は、生活費を用意しています。
 ミズカラくん
ミズカラくん心の余裕を持つためです。
安定した収入が得られるまでの期間は人によって異なります。
1ヶ月で成功する人もいれば、半年かかる人もいるでしょう。
成功する人は、最低でも半年〜1年分の生活費を事前に確保しています。
生活費に余裕があれば、焦って値下げしたり、無理な契約を取ったりしなくてよいでしょう。
心の余裕は、冷静な判断と長期的なビジネス戦略につながるのです。
失敗するリスクを想定している
成功する人は、事前に「失敗したらどうするか」を具体的に決めています。
 ミズカラくん
ミズカラくんリスクと対策を考えています。
たとえば、「半年で利益が出なければ再就職する」と決めて行動するケースです。
生活費がなくなり、生活に苦しむリスクを減らしています。
脱サラは、撤退ラインや資金の上限を設定しておくと、致命傷を避けられます。
リスクを冷静に見極められる人ほど、長く事業を続けられるのです。
脱サラをやめとけと言われても成功させる4つのポイント

脱サラをやめとけと言われても成功させるポイントは、以下の通りです。
- 事業計画をしっかりと立てる
- まずは事業を小さく始める
- 副業で経験を積んでおく
- 退職前から顧客を探しておく
事業計画をしっかりと立てる
脱サラで成功するには、具体的な事業計画が必要です。
 ミズカラくん
ミズカラくん感覚や勢いだけではだめです。
たとえば、「毎月の必要売上」や「半年後の目標顧客数」を数値化する。
自分が何をすべきか、行動が明確になるでしょう。
事業計画では、以下のような内容を細かくシミュレーションします。
- 収益モデル
- ターゲット層
- 競合分析
- 資金計画
計画があることで、途中での軌道修正もスムーズに行えるでしょう。
まずは事業を小さく始める
いきなり大規模で始めず、小さく事業を進めましょう。
 ミズカラくん
ミズカラくん初期投資やリスクが大きくなります。
たとえば、店舗ビジネスを行う場合。
ポップアップストアやイベント出店から始める方法もあります。
いきなり、大きな店舗で始める必要はないでしょう。
まずは小規模でテスト運営し、需要と課題を把握することが大切です。
小さな成功体験を積み重ねることで、自信と資金を確保できます。
副業で経験を積んでおく
本格的に独立する前に、副業で同じ業種の仕事を経験しておきましょう。
 ミズカラくん
ミズカラくん独立後の不安を大きく減らせます。
たとえば、飲食店を開く場合。
開業前に飲食店での勤務経験を積み、仕入れや接客の流れを学びます。
実際の顧客対応や案件管理を経験することで、独立後にできることも増えるでしょう。
事前の経験がある人ほど、初期の失敗を最小限に抑えられるのです。
退職前から顧客を探しておく
安定収入を確保するために、事前に顧客や案件を確保しておくことが理想です。
 ミズカラくん
ミズカラくん顧客ができてから独立しましょう。
ゼロから顧客探しを始めると、収益化までに時間がかかります。
開業したけど、数ヶ月は顧客を探している場合。
その数ヶ月間は、売り上げが立たない時間です。
SNSでの情報発信や人脈づくりなどで、営業活動を早めに始めておきましょう。
「退職初月から売上が立つ状態」を目指すことが成功への近道です。
脱サラをやめとけと言われた人の体験談

脱サラをやめとけと言われた堀内さんの体験談を紹介します。
◆悩んでいたこと
家族の反対にあい、脱サラするかどうか悩んでいました。
消防士だったので、安定収入があったことも反対された要因です。
辞めたいとは言ったものの、正直プレッシャー。
家族の生活を支えられるのか?というものはありました。
◆どうやって乗り越えたか
乗り越えるきっかけになったのは、キャリアコーチングです。
消防士を辞めて脱サラしたものの、うまくいっているとはいえず。
不安定で、モヤモヤした状態を抱えていました。
その時に支えになったのが「キャリスピ」
コーチのサポートを受けることで、仕事と向き合えるようになりました。
◆その後の変化
一番大きな変化は収入面です。
月商20万円程度だったのが、月商1,200万円に。
法人化し、3ヶ月で月商5000万円に到達。
自分の会社なので、家族との時間も自由にとれるようになりました。
脱サラして、環境が大きく変わったなと感じています。
脱サラをやめとけと言われた人からよくある質問
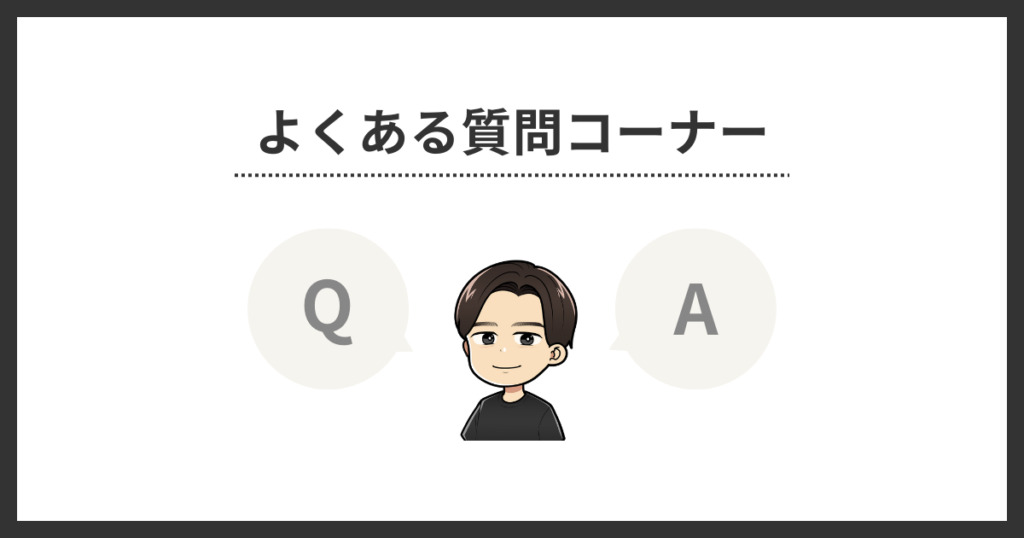
脱サラをやめとけと言われた人からよくある質問に回答します。
- 脱サラの平均年齢は?
- 脱サラするのに向いている人は?
- スキルなしでも脱サラはできる?
- 脱サラ失敗後の再就職は可能?
- 脱サラの平均年齢は?
-
日本政策金融公庫の調査によると、起業者の平均年齢は43.7歳でした。
直前の職業については70.9%が正社員・正職員です。
会社員からの企業が3人に2人以上となる結果でした。
- 脱サラするのに向いている人は?
-
脱サラするのに向いている人は、以下のような人です。
脱サラするのに向いている人の特徴- 計画性がある人
- 自己管理能力が高い人
- 柔軟に学び続けられる人
- 資金・人脈がある人
事前の準備をどれだけできているかが大切になります。
- スキルなしでも脱サラはできる?
-
スキル無しでも脱サラは可能です。
ただし、難易度は高くなります。
スキルがない場合は、まず副業や資格取得でスキルを身につけることがおすすめです。
副業からのスモールスタートで経験を積むほうが安全でしょう。
- 脱サラ失敗後の再就職は可能?
-
脱サラ失敗後の再就職は可能です。
実際、多くの人が再就職に成功しています。
脱サラの経験は、営業力・企画力・自己管理能力などがアピールできる武器になります。
ただし、ブランクが長い場合は、再就職までに時間がかかる可能性があります。
失敗後すぐに動けるように、資格やスキルを維持しておくと有利です。
派遣や契約社員、短期アルバイトなどから再スタートして正社員に戻るケースも多いです。
まとめ:脱サラをやめとけと言われる理由5選!しっかりと準備をしておこう

脱サラしたい!というと、反対にあうことは多いものです。
 ミズカラくん
ミズカラくんその背景には、以下のような理由があります。
- 収入がなくなるリスクがあるから
- スキル不足で失敗する場合があるから
- 競合他社や市場が厳しいから
- プレッシャーや不安を感じやすいから
- 初期投資がかかるケースもあるから
脱サラを成功させることは、簡単なことではありません。
しっかりと準備しないと、失敗してしまうでしょう。
 ミズカラくん
ミズカラくんまた、脱サラを成功させるには覚悟も大事。
「今の仕事が嫌だから」のような、なんとなくの気持ちでは、失敗するといえます。
脱サラするか悩んでいるあなたにおすすめなのが、キャリアコーチング
 ミズカラくん
ミズカラくん自分のキャリアについて、一度真剣に考えてみましょう。
キャリアコーチングを受けることで、自分の道筋を見つけられた方もいます。
インタビューの様子を動画にしたので、こちらもぜひご覧ください。