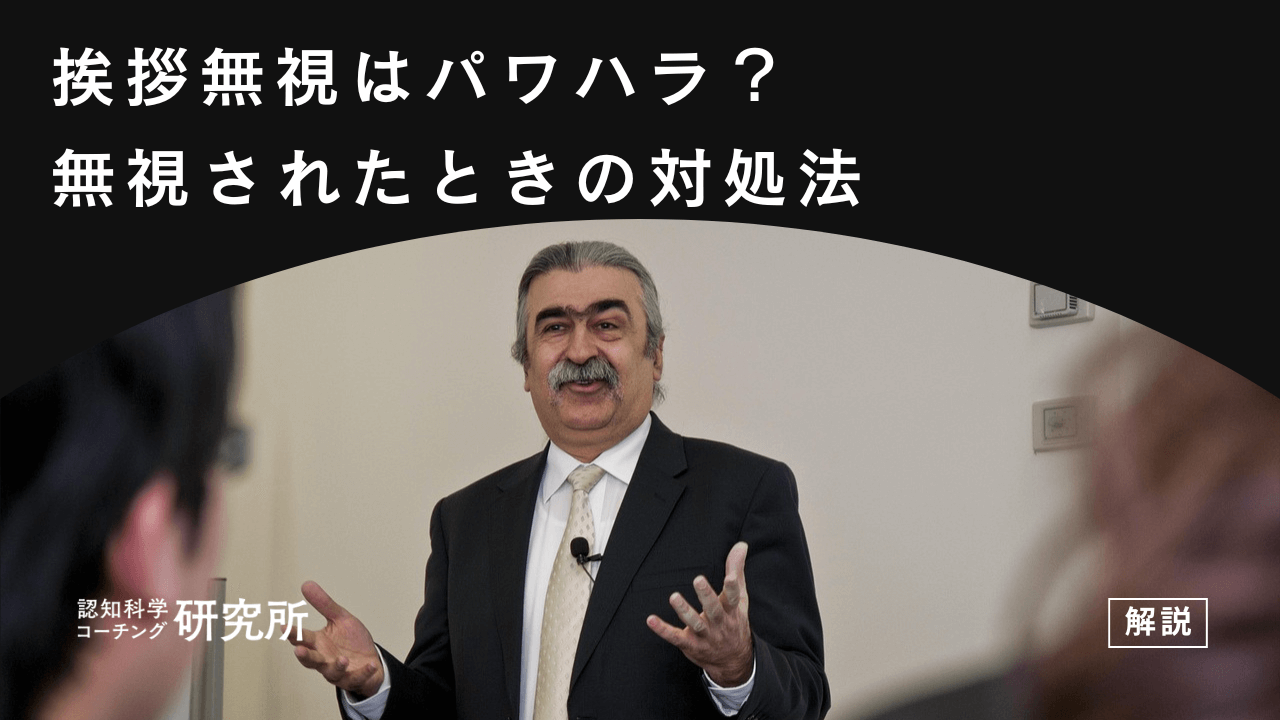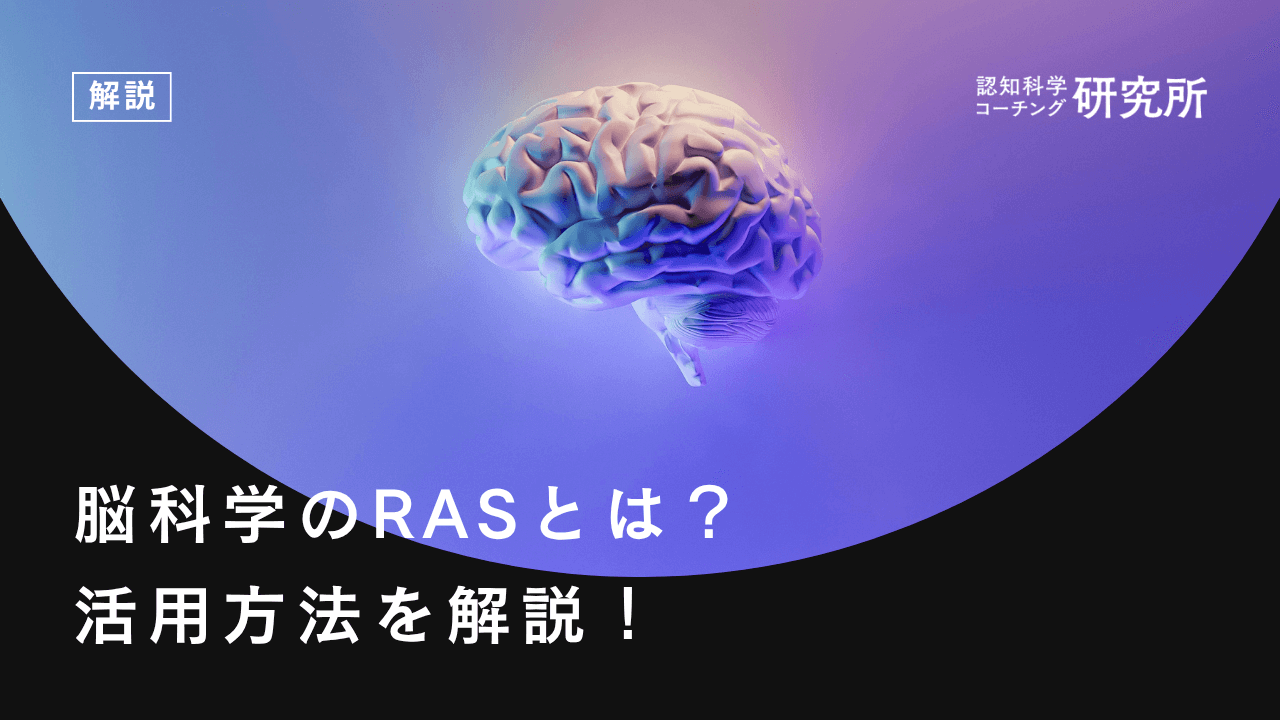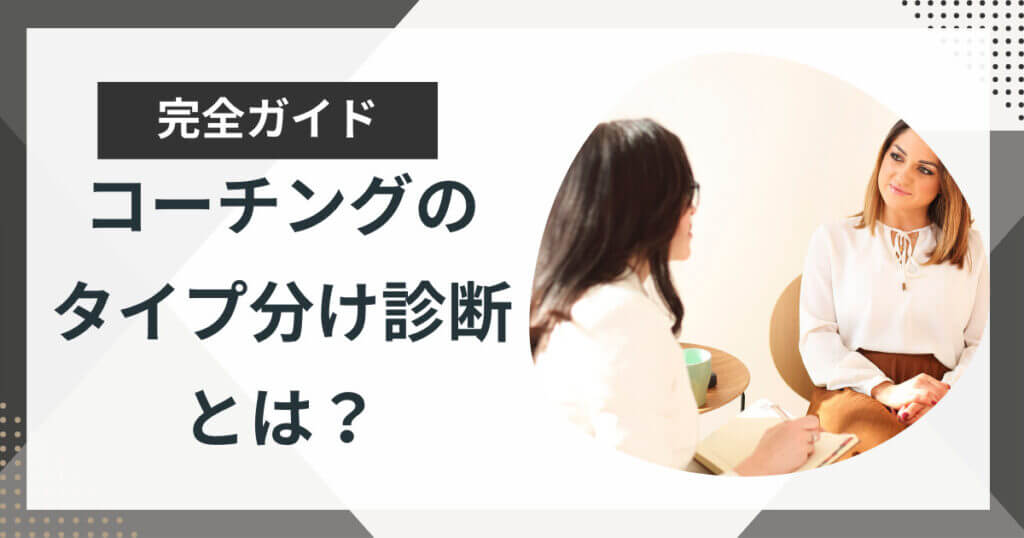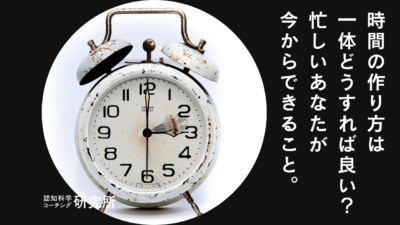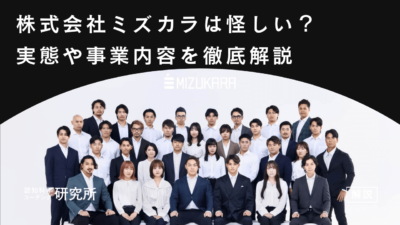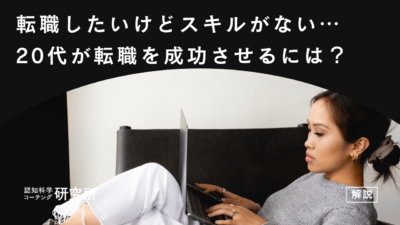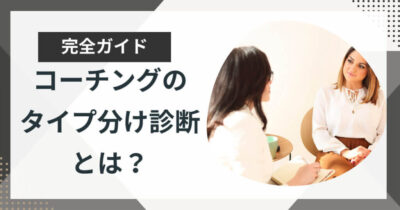当事者意識とは?
部下に当事者意識を持たせるには?
部下が当事者意識を持つ一体感のある組織を作る方法について、わかりやすく解説します。
「部下に当事者意識が感じられない」
「部下に当事者意識を持たせるにはどうすればいい?」
「当事者意識が生まれないのはなぜ?」
マネジメントで課題になるのが、部下の当事者意識。
 島田隆則
島田隆則仕事を任せても当事者意識がなく、悩むことも多いでしょう。
部下の当事者意識を持たせるために大切なのは、「主体性」
ただ仕事を与えているだけでは、当事者意識は生まれません。
この記事では、当事者意識がない部下への対応をどうするかについて解説。
最後まで読めば部下の当事者意識が高まり、一体感のある組織を実現できるはずです。
当事者意識のない部下にアプローチするには、マネジメント手法が大事。
認知科学に基づいたマネジメントを習得し、組織の一体感を作り上げましょう。
具体的なマネジメント手法を動画にまとめたので、こちらをぜひご覧ください。
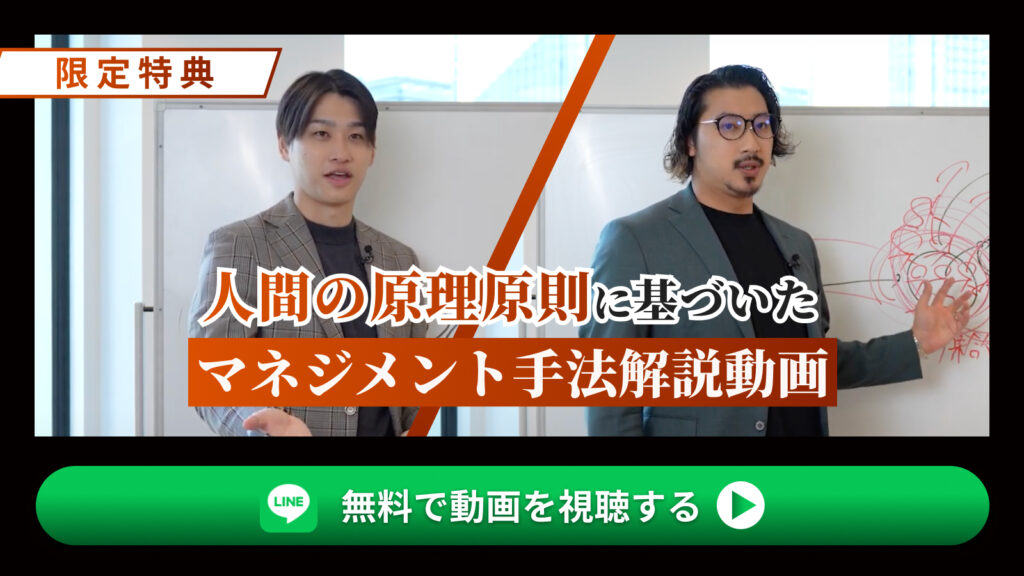
当事者意識とは?

当事者意識とは、「会社が向かう未来を自分の人生のように握れる状態」のことです。
社長やリーダーが持つビジョンに飲み込まれ、実現したいと感じる。
そのビジョンが自分の人生だと思うような状態です。
 島田隆則
島田隆則実際、実現は大変です。
当事者意識がないと、部下を率いるのは大変。
制度で釣ったり、給料で釣ったりしなければならなくなるのです。
当事者意識に重要な「主体性」と「自主性」
当事者意識を持つためには、主体性と自主性の違いを知ることが大切です。
それぞれの違いは、以下の通り。
- 主体性:自らの意思や判断に基づいて、自分の責任のもと行動すること
- 自主性:ある程度決められたことを自ら率先して行う態度
 島田隆則
島田隆則大きな違いは、「決められた範囲内で」動くかどうか。
自主性の場合、決められた範囲や枠組みの中で行動します。
自分の考えとは言いつつ、責任を持つのは上司。
上司が決めた枠組みの中で、ある程度自由に行動しています。
一方で、主体性は自分の責任で動く行為です。
自分の行動に自分で責任を持ち、目標に向けて行動する。
 島田隆則
島田隆則主体性が発揮されたときに、やっと組織の自走が生まれます。
主体性と自主性の違いについては、下記の動画もご覧ください。
当事者意識の認識を揃える必要もある
当事者意識を持つためには、それぞれの認識を揃える必要もあります。
たとえば、チームとして売り上げを出そうとする場合。
リーダーは、「組織全体のことを考えてほしい」と思っている。
一方で、部下は「自分のことを完璧にできるのが大事」だと思っている。
 島田隆則
島田隆則これでは、お互いの認識は、ずれたままです。
リーダーからすると、組織全体のことを考えていない部下に、当事者意識がないと思う。
部下は、自分の業務に自分で責任を持っているから、当事者意識があると感じている。
このずれが、当事者意識のない状況を生みだす場合があります。
当事者意識を持ってもらうためには、当事者意識の認識を合わせることも大切です。
当事者意識が仕事で大事な理由

当事者意識が仕事で大事な理由は、以下の通りです。
- 主体性をもって仕事ができる
- 従業員のモチベーションが高まる
- 責任感を持って仕事ができる
- 意思決定の速度があがる
主体性をもって仕事ができる
当事者意識を持つことにより、主体性をもって仕事ができます。
 島田隆則
島田隆則自分の責任で行動できます。
主体性が生まれれば、組織のことを考えられるように。
組織のビジョン実現に向けて、自分は何ができるかを考えられます。
指示を待たなくても、自分で行動する主体性が生まれるでしょう。
従業員のモチベーションが高まる
当事者意識は、従業員のモチベーションアップにも効果的です。
 島田隆則
島田隆則「もっとやろう」と思えるようになります。
当事者意識を持つことで、やるべきことが明確に。
目標も自分で決めることができ、モチベーションがあがります。
人に決められた目標では、やる気はだんだんと下がるだけ。
当事者意識を持つことで、モチベーションアップにつながるのです。
責任感を持って仕事ができる
当事者意識を持つことで、責任感も生まれます。
 島田隆則
島田隆則自分の責任のもとで、行動できます。
人から言われた仕事では、責任感は生まれないもの。
上司が責任をとると考えるので、当事者意識も生まれません。
当事者意識があることで、自分の責任で行動するように。
「自分がやるべきだ」と考えられるようになるのです。
意思決定の速度があがる
意思決定の速度が上がることも、当事者意識を持つメリットです。
 島田隆則
島田隆則自分の責任と判断で行動するからです。
当事者意識を持つ人材は、自分のやるべきことを自分で考えます。
上司の指示を待ったり、判断を待ったりする時間が減るでしょう。
 島田隆則
島田隆則当事者意識がないと、指示があるまで動けない状況に。
当事者意識を持つことは、意思決定の速度にもプラスになります。
当事者意識がない部下が発生する4つの原因

当事者意識がない部下が発生する背景には、以下の4つがあります。
- 指示に従うだけになっている
- 目の前の仕事に追われている
- 役割が決まっていない
- 組織の一体感がない
指示に従うだけになっている
当事者意識がない部下が発生するのは、指示に従うだけだからです。
 島田隆則
島田隆則責任感も主体性も生まれません。
上司の指示に従う状態は、自分で考えない状態です。
「言われたことだけやってればいい」と感じ、当事者意識は生まれません。
自分で考えて行動する状況でないと、当事者意識は起こらないでしょう。
目の前の仕事に追われている
目の前の仕事に追われている状態も、当事者意識は生まれません。
 島田隆則
島田隆則全体を考える暇がないからです。
目の前の仕事に追われていると、仕事の目的や目標を見失います。
「とりあえず目の前の仕事を終わらせよう」と考えるだけに。
「この仕事が何につながっているのかわからない」
「なんのために仕事をしているのかわからない」
「何を期待されているのかわからない」
目の前の仕事に必死になってしまい、「この仕事が終わればいい」となってしまう。
自分のことしか考えないようになり、当事者意識はなくなってしまうのです。
役割が決まっていない
役割が決まっていない状態も、当事者意識は薄くなります。
 島田隆則
島田隆則責任がないからです。
役割がない状態は、責任が不明確な状態。
仕事や立場に対して、自分事として考えられません。
「誰かに言われたから」で仕事をする状態。
自分のなすべきことがわからず、当事者意識が持てないのです。
組織の一体感がない
組織の一体感がない状態も、当事者意識を持てません。
 島田隆則
島田隆則行動する目的がないからです。
当事者意識を持てるのは、組織の一員として行動するから。
組織の目的や目標を果たすために、当事者意識を持って行動しようとします。
 島田隆則
島田隆則しかし、組織の一体感がないと、メンバーはバラバラに行動するだけ。
当事者意識を持てる対象がないので、当事者意識が生まれないのです。
当事者意識がない職場の3つの特徴

当事者意識がない職場の特徴は、以下の通りです。
- 職場の風通しが悪い
- 協力する体制がない
- 従業員のモチベーションが低い
職場の風通しが悪い
職場の風通しが悪いと、当事者意識は生まれません。
 島田隆則
島田隆則組織のために行動しようと思わないでしょう。
たとえば、意見をしても上司に受け入れてもらえない。
主体的に行動しようとすると、「勝手なことをするな」と言われる。
 島田隆則
島田隆則行動する意欲がなくなり、当事者意識は下がります。
職場の風通しが悪い環境では当事者意識は生まれず、自分のことを優先してしまうでしょう。
協力する体制がない
協力する体制がない職場も、当事者意識は生まれません。
 島田隆則
島田隆則自分のことばかり考えてしまいます。
協力体制がない組織は、それぞれが勝手に動いている状態。
 島田隆則
島田隆則個人の成果は出ても、組織としての成果は期待できません。
自分のために行動しているけど、組織への帰属感は薄い。
当事者意識はなく、バラバラの組織になってしまいます。
従業員のモチベーションが低い
従業員のモチベーションが低い場合も、要注意です。
 島田隆則
島田隆則言われたことだけやろうとします。
主体性が発揮されるのは、モチベーションが高いから。
「組織のために」「リーダーのために」で行動できます。
モチベーションがないと、最低限のことだけをやる状態に。
 島田隆則
島田隆則責任感もなく、ただ仕事をこなすだけです。
モチベーションを高く持てなければ、当事者意識を持つことも難しいでしょう。
部下の当事者意識を高める4つの方法

部下の当事者意識を高めるには、以下の4つが効果的です。
- 自分で考える機会を作る
- 組織としての目標を明確にする
- 責任のある仕事を任せる
- コーチングを導入する
自分で考える機会を作る
部下の当事者意識を高めるために、部下が自分で考える機会を作りましょう。
 島田隆則
島田隆則指示待ちからの脱却です。
指示を待っている状態は、主体性が発揮されない状態。
責任感はなく、当事者意識は生まれません。
人は自分で考えて行動するからこそ、責任感を持ちます。
指示を与えるのではなく、部下が自分で考えて行動する環境を作ってみましょう。
組織としての目標を明確にする
組織として目標を明確にするのも、当事者意識を持つためには大切です。
 島田隆則
島田隆則向かう先がないと、主体性は生まれません。
当事者意識が生まれるのは、明確な目標があるから。
「実現するために、自分は〇〇したい」が生まれます。
 島田隆則
島田隆則組織の目標がない状態では、自分事化もできないでしょう。
まずは組織として、何を成し遂げたいのか明確にすることが大切です。
責任のある仕事を任せる
仕事を任せる際は、責任のある仕事を任せましょう。
 島田隆則
島田隆則自分事化する第一歩です。
いきなり主体性を発揮してもらうのは、正直難しいもの。
たとえば、新入社員に自分で考えて、成果を出させるのは酷です。
まずは責任のある仕事を任せて、責任を体感することが大事。
自主性を持って仕事をする状態を経験し、主体性に変えていくのです。
当事者意識を持つ第一歩として、責任のある仕事を任せてみましょう。
コーチングを導入する
当事者意識をもたせるために、コーチングを導入してみましょう。
 島田隆則
島田隆則アプローチ方法を変えることも大事です。
リーダーにありがちなマネジメントが、指示を与えるだけのマネジメント。
部下に考える余地がなく、責任感が生まれません。
コーチングを導入することで、主体性を持てる人材にレベルアップ。
自分で目標を定めて行動するので、責任感が生まれるのです。
認知科学コーチ養成講座で、認知科学に基づいたマネジメントを学びましょう。
詳細を下記のページで紹介しているので、当事者意識を持たせるマネジメントを学んでください。
\ 400名以上が申込みに殺到!/
※無料説明会実施中!
当事者意識が意識がない状態に関するよくある質問
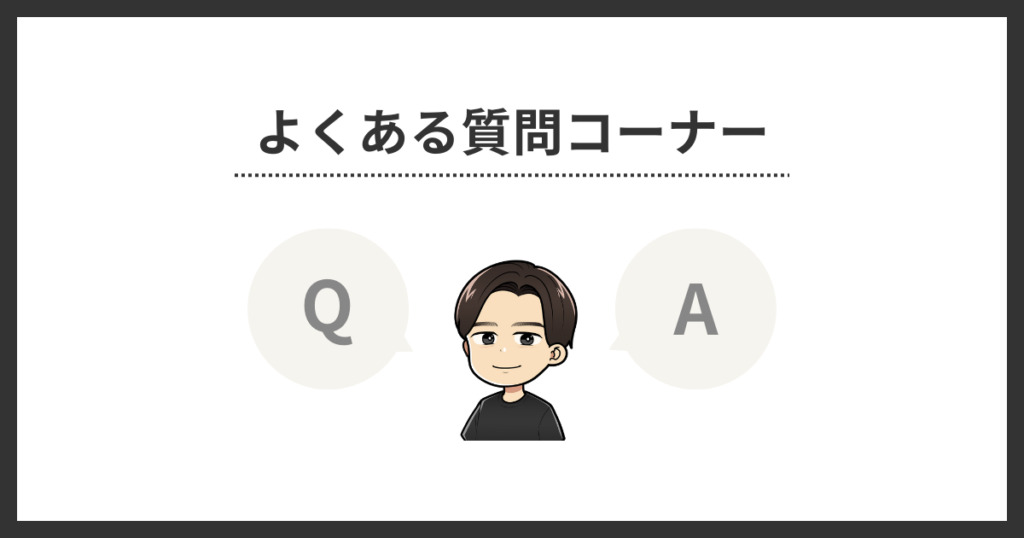
当事者意識が意識がない状態に関するよくある質問に回答します。
- 当事者意識がない人の特徴は?
- 部下をダメにする上司の特徴は?
- 当事者意識の欠如とはどういうことでしょうか?
- 当事者意識がない人の特徴は?
-
当事者意識がない人の特徴には、以下のようなものがあります。
当事者意識がない人の特徴- 問題に興味関心がない
- 組織の一員だと感じていない
- 人任せにしている
- 諦めが早い
- 自分を優先している
- 責任を負いたくない
- 部下をダメにする上司の特徴は?
-
部下をダメにする上司の特徴は、以下の通りです。
部下をダメにする上司の特徴- 一方的なコミュニケーションをとる
- 失敗を責め続ける
- 絶対に自分が正しいと思い込んでいる
- 感情的になりやすい
- 当事者意識の欠如とはどういうことでしょうか?
-
当事者意識の欠如は、言われたことをやっているだけの状態のことです。
仕事や問題に対して、あまり興味がありません。
指示に従って、満足している。
責任を持たずに、自分事化できていない状態を指します。
まとめ:当事者意識がない部下が発生するのはなぜ?意識の高め方を解説

当事者意識がない部下が発生する理由には、以下の理由があります。
- 指示に従うだけになっている
- 目の前の仕事に追われている
- 役割が決まっていない
- 組織の一体感がない
特に、指示に従うだけの主体性がない状態だと、当事者意識はうまれないでしょう。
 島田隆則
島田隆則部下に当事者意識を持ってもらうには、マネジメント手法が大事。
日々の接し方によって、部下の仕事に対する姿勢や取り組み方が変わります。
認知科学に基づいたマネジメント手法なので、どのような組織でも成果が出ます。
マネジメント手法は知識を入れるだけではなく、実践で発揮できることが重要です。
知識を体現できる環境が整った、認知科学コーチ養成講座で学びましょう。
認知科学コーチ養成講座がどのような講座なのかは、下記のページをぜひご覧ください。
\ 400名以上が申込みに殺到!/
※無料説明会実施中!