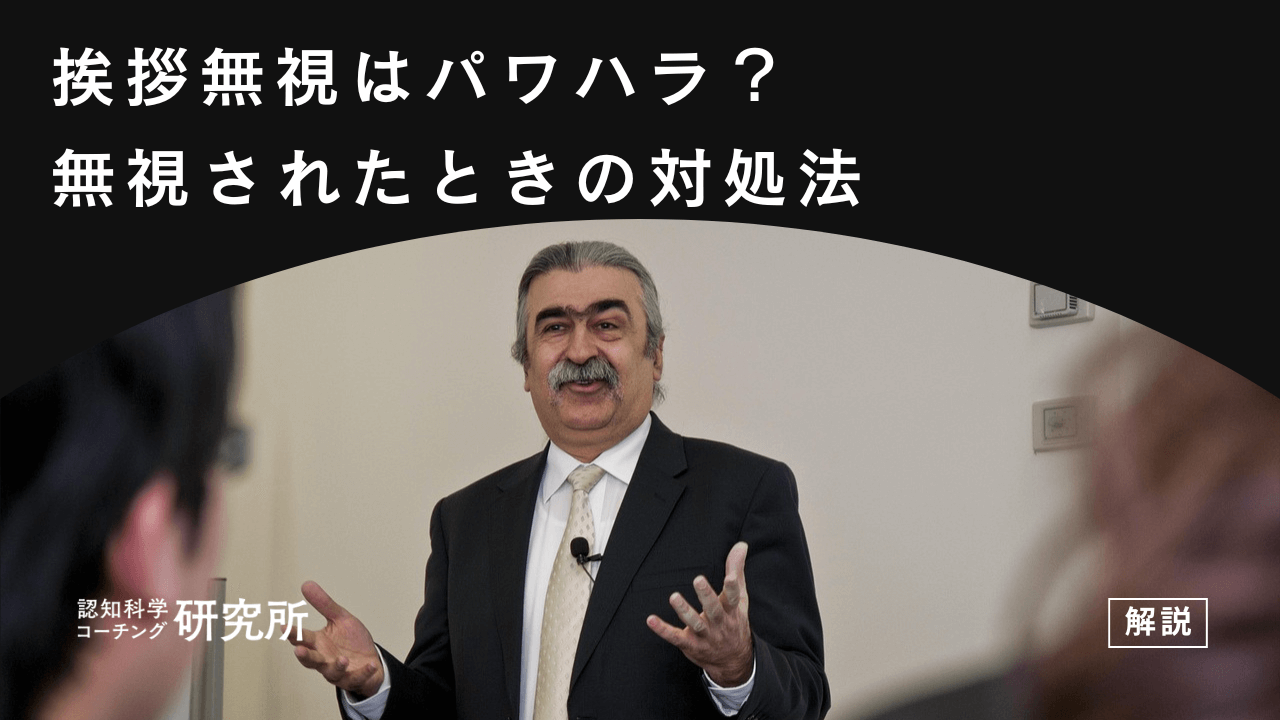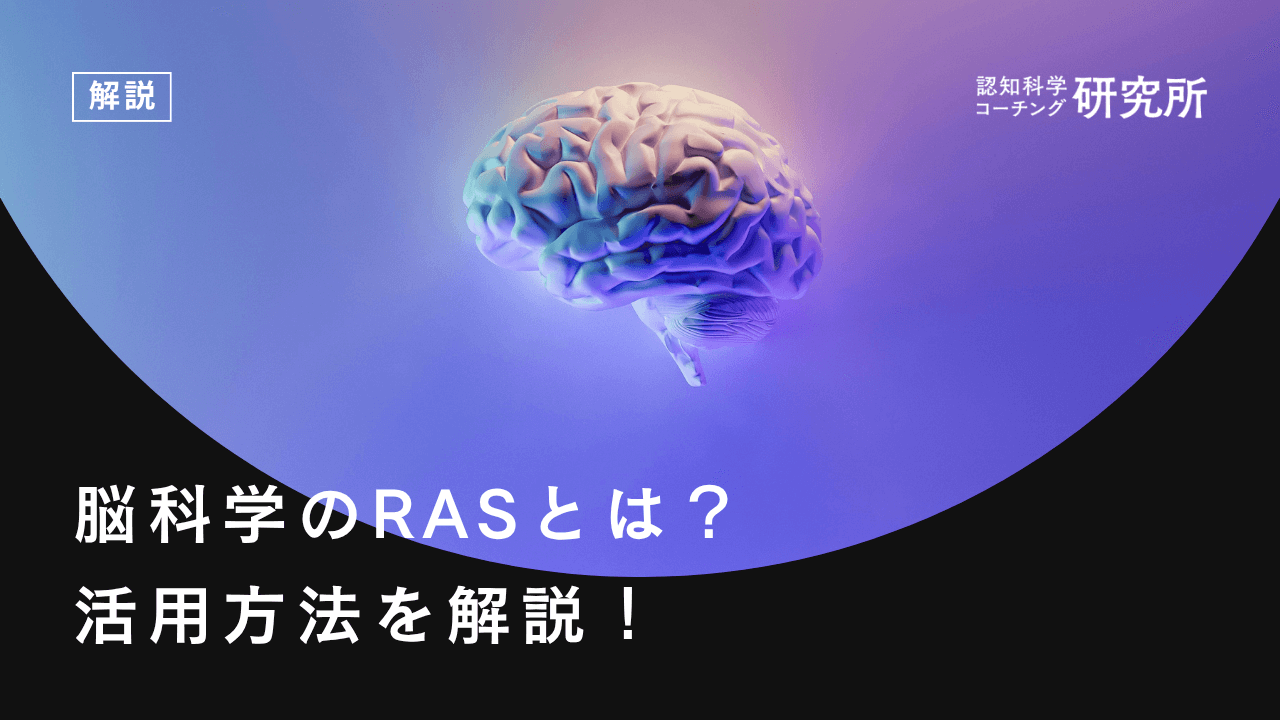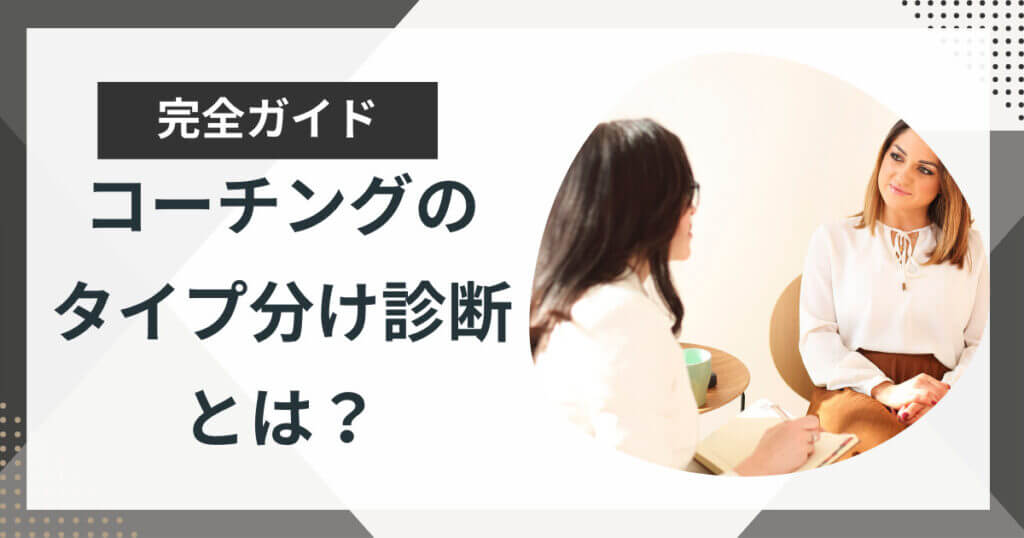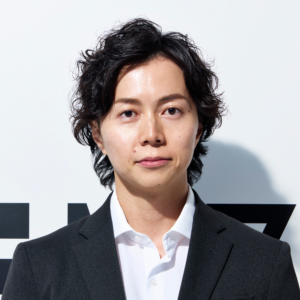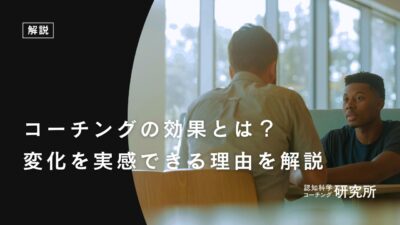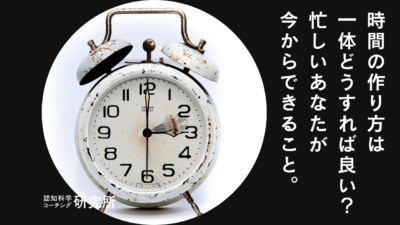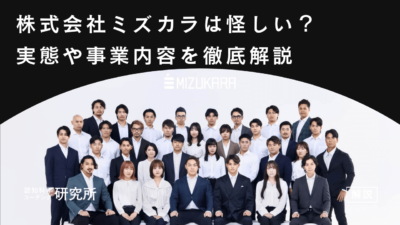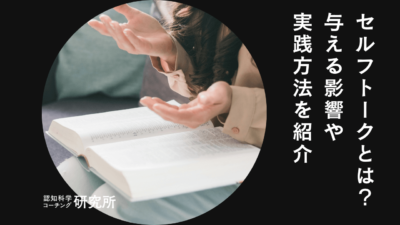内発的動機とは?
内発的動機を高める方法は?
この記事では、内発的動機を高めて現状を変える解決策を分かりやすく解説します。
「内発的動機って何?」
「内発的動機を高める方法とは?」
「内発的動機と外発的動機の違いって?」
やる気や行動力を高めるための内発的動機の伸ばし方に悩んでいる方も多いのではないでしょうか?
この記事では、15,000人以上のキャリアの悩みを解決してきたプロのキャリアコーチが「内発的動機の高め方」について解説しています。
この記事を読むと内発的動機を高められて、自分や部下・チームの意欲向上に繋がり、成果や人間関係がプラスに変化します。
「内発的動機を高める」ためには自分の強みを知ることが非常に効果的です。
内発的動機は【自分らしさ】【やりがい】など、内側から湧き上がる意欲が土台になります。
以下で無料で「強みが分かるワークシート」を配布しているので、自分の強みを把握し、内発的動機を高めていきましょう。
内発的動機とは?

内発的動機について、外発的動機との違いについて分かりやすく解説していきます。
- 内発的動機の定義と意味
- 外発的動機との違い
内発的動機の定義と意味
内発的動機とは、自分の内側から湧き上がる興味や関心、やりがいによって行動が促される心理状態のことを指します。
つまり、金銭的な報酬や外部からの評価に依存せず「やってみたい」「もっと知りたい」「挑戦したい」という自分自身の欲求や意欲が原動力となる動機づけです。
内発的動機は、自己決定感や自己有能感が満たされることで強まり、行動が自律的かつ持続的になります。
例えば、趣味で熱中したり、仕事で新しいスキルを身につけたりする時の「楽しい」という感覚が内発的動機にあたります。
自分の強みを知ると内発的動機を高められて、夢中になれる仕事に出会えます。
自身の強みがわからない人向けに、15,000人以上のキャリアの悩みを解決してきたプロのキャリアコーチが「強みがわかるワークシート」を無料で配布しています。
以下のボタンから簡単に受け取れるので活用してください。
外発的動機との違い
【内発的動機と外発的動機の違い】
| 内発的動機 | 外発的動機 | |
| 定義 | 活動そのものから得られる満足感で行動する動機 | 外部からの報酬や罰を避けるために行動する動機 |
| 動機の源泉 | 個人の内面 興味、好奇心、達成感 | 外部環境 報酬、評価、罰則 |
| 具体例 | ・趣味の読書 ・好きな分野の学習 ・創作活動 ・スポーツを楽しむ | ・給料のための仕事 ・成績のための勉強 ・罰を避けるための行動 ・他者からの評価狙い |
| 持続性 | 高い 長期間継続しやすい | 低い 報酬がなくなると継続困難 |
| パフォーマンス | 創造性や質の高いパフォーマンス | 単純作業では効果的だが創造性は低下 |
| 満足感 | 活動中から満足感を得られる | 結果を得た時のみ満足感 |
| ストレス | 低い 楽しみながら取り組める | 高い プレッシャーを感じやすい |
| 学習効果 | 深い理解と応用力が身につく | 表面的な学習になりがち |
| 自立性 | 高い 自分で選択している感覚 | 低い コントロールされている感覚 |
外発的動機は短期的な行動変容には効果的ですが、持続性に欠けやすく、場合によっては内発的動機を損なうリスクもあります。
内発的動機は活動そのものに満足感や意味を見出すため、長期的かつ自発的な行動につながることが特徴です。
内発的動機を高めるための3つの心理学的背景

内発的動機を高められるようになるには、3つの心理学的背景を理解することが効果的です。
- 自己決定理論
- マズローの欲求階層説
- アンダーマイニング効果と動機付けのバランス
自己決定理論
自己決定理論は、アメリカの心理学者エドワード・デシとリチャード・ライアンが提唱した動機づけ理論で、内発的動機づけの理解において非常に重要な役割を果たしています。
- 自律性(自分で決めたいという欲求)
- 有能感(自分は能力があると感じたい欲求)
- 関係性(周囲の人と良好な関係を築きたい欲求)
基本的心理欲求が満たされると、内発的動機が高まり、自発的に主体的な行動を取りやすくなります。
 ミズカラくん
ミズカラくん持続的なモチベーションに繋がります。
内発的動機を高めるためには、具体的なGOAL設定も大切です。
GOALが設定されていると行き先のイメージがつきやすいため、モチベーションの向上も維持できます。
15,000人以上のキャリアの悩みを解決してきたキャリアコーチングのプロが作成した「GOAL設定のワークシート」を使用してみましょう。
下記ボタンから簡単に受け取れるので、ぜひGOAL設定に役立ててください。
マズローの欲求階層説
マズローの欲求階層説は、人間の欲求を5段階に分類した有名な心理学理論です。
1、生理的欲求
人間が生きていくうえで欠かせない基本的な欲求で、食事・睡眠・呼吸などの本能的な欲求のこと。
まずはこの欲求が満たされることが必要。
2、安全の欲求
身体的・経済的に安全で安定した状態を求める欲求。
事故や病気からの安全、安定した職や住居の確保が含まれる。
3、社会的欲求(所属と愛の欲求)
友人や家族、職場の同僚など、社会的なつながりや所属感、愛情を求める欲求。
人間関係の中で受け入れられたいという欲求を指す。
4、承認欲求(尊重の欲求)
他者から認められたい、尊敬されたい、自尊心を満たしたいという欲求。
自己評価の向上や地位の獲得も含まれる。
5、自己実現の欲求
自分の能力を最大限に発揮し、成長や創造性を追求したいという最高次の欲求。
自己の可能性を実現することに喜びを感じる。
生理的欲求や安全の欲求などの基本的な欲求が満たされたうえで、自己実現欲求といった高次の欲求が重要になります。
内発的動機は、自己実現欲求に密接に関係していて、満足感ややりがい、自己成長への意欲が高まる段階で強く働きます。
アンダーマイニング効果と動機付けのバランス
アンダーマイニング効果とは、外発的動機(報酬など)が内発的動機(本来の興味・楽しさ)を弱めてしまう現象です。
- Before:子供が本を読むのが大好き(内発的動機)
- 介入:「本を1冊読んだら100円あげる」と親が報酬制を導入
- After:報酬がなくなると読書をしなくなる(内発的動機が低下)
- Before:プログラマーが新技術の習得を楽しんでいる
- 介入:会社が「資格取得で報奨金5万円」制度を導入
- After:報奨金目当てになり、純粋な学習意欲が低下
内発的動機を高める際には、外発的動機との適切なバランスが求められます。
外発的報酬は補助的に用い、主体的な選択や自律性を重視する環境づくりが大切です。
内発的動機を高める5つのメリット

以下では個人および組織の成長に大きく貢献する、内発的動機を高めるメリットを紹介します。
- モチベーションの持続や自己成長につながる
- 生産性や創造性が向上し高品質な成果を生む
- 自主性と責任感が強化され能動的な行動を促す
- チームの協力関係やエンゲージメントが向上
- 仕事に対しての満足感や充実感が得られる
モチベーションの持続や自己成長につながる
内発的動機に基づく行動は、外部からの報酬やプレッシャーに依存しないため、長期的にモチベーションを維持しやすい特徴があります。
自らの興味や価値観に基づいて取り組むため、学びや成長に対する意欲が自然に高まり、スキルアップや資格取得に積極的に取り組む姿勢が強まります。
 ミズカラくん
ミズカラくん苦難にも粘り強くチャレンジできます。
生産性や創造性が向上し高品質な成果を生む
内発的動機が高いと、仕事に没頭しやすくなり、効率よく質の高い成果を出せます。
さらに、好奇心や探求心が刺激されて、新しいアイデアが浮かび、創造的な取り組みが促進されます。
 ミズカラくん
ミズカラくん組織の活性化や競争力強化にも創造性は必要です。
自主性と責任感が強化され能動的な行動を促す
内発的動機に基づく行動は、自分で決めて行動する自律性が高まります。
結果として、自分の仕事に責任を持ち、能動的に課題を見つけ解決しようとする姿勢が強くなります。
 ミズカラくん
ミズカラくん指示待ちの状態から脱却しましょう。
成果の質や量が向上することが期待されます。
チームの協力関係やエンゲージメントが向上
内発的動機が高いメンバーが増えると、メンバー同士の信頼や協力関係が築かれやすくなります。
 ミズカラくん
ミズカラくん全体の雰囲気が良いチームが理想です。
自発的なコミュニケーションや支援の輪が広がることで、組織のエンゲージメントも高まり、目標達成に向けての一体感が生まれます。
仕事に対しての満足感や充実感が得られる
内発的動機を持つと、仕事そのものから喜びややりがいを感じやすくなります。
外的な報酬に頼らず、活動自体に価値を見出すため、達成感や自己効力感が深まり、仕事に対する満足感や幸福感が高まります。
 ミズカラくん
ミズカラくん長期的なやる気の源泉となるでしょう。
内発的動機を高めた場合にみられる5つのデメリット
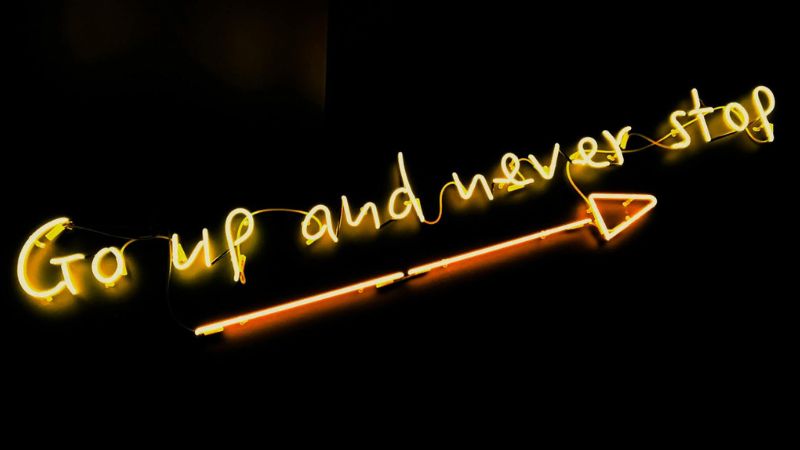
以下では、内発的動機を高めた場合のデメリットをまとめています。
- 動機形成まで時間がかかり即効性は低い
- 個人差が大きくすべての人に効果的とは限らない
- 興味や関心が薄れモチベーションが急激に低下する
- 自律性の過度な重視がストレスになる
- 外発的動機とのバランス調整が難しい
動機形成まで時間がかかり即効性は低い
内発的動機は自分の内側から湧き上がる興味や関心に基づくため、形成に時間がかかる傾向があります。
 ミズカラくん
ミズカラくん短期間での即効性を求める状況には向いていません。
新しい仕事やプロジェクトに対して、すぐに強い内発的動機を持つのは難しく、徐々に関心が高まることが多いです。
個人差が大きくすべての人に効果的とは限らない
内発的動機は個人の価値観や興味、性格に大きく左右されるため、同じ施策でも効果が異なることがあります。
ある人には強い動機付けとなっても、別の人にはほとんど影響を与えないことがあります。
 ミズカラくん
ミズカラくん個別対応や多様なアプローチが必要になる場合が…。
興味や関心が薄れモチベーションが急激に低下する
内発的動機は、興味や関心が薄れてしまうと、モチベーションが急激に低下しやすい特徴もあります。
対象となる活動やテーマに対する興味が継続していることが前提です。
 ミズカラくん
ミズカラくん仕事のマンネリ化や達成感が得られずやる気が失われることも…。
自律性の過度な重視がストレスになる
内発的動機を重視するあまり、自律性に過剰な期待や負担がかかると、逆にプレッシャーやストレスにつながることがあります。
 ミズカラくん
ミズカラくん全て自己責任の状況は能力や経験不足で大きな負担を感じることも。
外発的動機とのバランス調整が難しい
内発的動機は長期的な成長や持続的なやる気に効果的ですが、外発的動機(報酬や評価)とのバランスが重要です。
外発的な報酬が適切に活用されないと、内発的動機を損ねる場合があります(アンダーマイニング効果)。
状況に応じて内発的・外発的動機を適切に組み合わせることが求められます。
 ミズカラくん
ミズカラくんデメリットを理解したうえで個人差や負荷への配慮を行うことが重要!
内発的動機を高める具体的な行動5つ

内発的動機を高めるために必要な行動を紹介します。
- 自分が決めた目標で段階的な達成体験を積む
- 得意分野や自分の強みを仕事に活かす
- アイディアや意見を発信しフィードバックをもらう
- 新しい業務に自分からチャレンジ
- 日常のコミュニケーションや感謝を意識
自分が決めた目標で段階的な達成体験を積む
自己効力感と自律性の両方を同時に育てることができるため、自分で設定した目標を達成することは、内発的動機を効果的に高められます。
具体例
- 大きな目標を週単位・日単位の小さなタスクに分割する
- 「今日はこれができた!」という成功体験を毎日積み重ねる
- 達成度を可視化して成長を実感する
 ミズカラくん
ミズカラくん次の挑戦への意欲が湧き持続的なモチベーション向上に繋がります。
得意分野や自分の強みを仕事に活かす
自分の得意分野や強みを仕事に活かすことで、有能感を実感し内発的動機が高まります。
 ミズカラくん
ミズカラくん強みを発揮できる環境では仕事自体が楽しく感じられます。
具体例
- コミュニケーション得意→チーム調整役を積極的に担う
- 分析が得意→データ分析業務に関わる機会を増やす
- 創造性が強み→企画立案や改善提案に参加する
強みを認められる環境は自己肯定感を高め、さらなるモチベーション向上の好循環を生み出します。
アイディアや意見発信しフィードバックをもらう
積極的な意見発信とフィードバック受信により、自律性と社会的つながりの両方を育むことができます。
 ミズカラくん
ミズカラくん「自分も組織の一員として貢献している」という実感を得られます。
具体例
- 会議で改善案を積極的に提案する
- 同僚や上司に業務効率化のアイディアを共有する
- プロジェクトに対する自分なりの視点を伝える
コミュニケーションサイクルが内発的動機を増幅させ、より主体的な行動を促進します。
新しい業務に自分からチャレンジ
未知の分野や難易度の高い業務への自主的なチャレンジは、内発的動機を強力に刺激します。
新たな挑戦は自己成長を実感させ、達成感や自己効力感を高めるためです。
 ミズカラくん
ミズカラくん自分から選択したチャレンジは自律性も育みます。
具体例
- 担当外の業務にも積極的に関わる
- 新しいスキルや資格取得に挑戦する
- 難しいプロジェクトに手を挙げて参加する
失敗を恐れず挑戦し続ける姿勢が、長期的なやる気の持続に直結します。
日常のコミュニケーションや感謝を意識する
日々の小さなコミュニケーションと感謝の表現は、職場での信頼関係を築き内発的動機の基盤となります。
 ミズカラくん
ミズカラくん感謝される経験は仕事の意味や価値を実感させます。
具体例
- 同僚の頑張りに「ありがとう」を伝える
- 困っている人に声をかけてサポートする
- 日常的な雑談で関係性を深める
人間関係の土台があることで、自発的に動く意欲が自然と引き出されます。
内発的動機が高まり仕事への向き合い方が向上した具体例4つ

内発的動機が高まり仕事への向き合い方が向上した具体例をご紹介します。
- 自発的な行動の変化
- 困難や壁への主体的な取り組み
- 目標に対する持続的なモチベーション
- メンバーの意欲向上と組織への影響
自発的な行動の変化
内発的動機が高まると、指示や強制を待つのではなく、自ら課題を見つけて積極的に行動できます。
(例)
・業務改善のアイデアを自主的に提案
・新しいスキルを自主学習したりする社員が増える
・職場全体の活性化につながる
困難や壁への主体的な取り組み
困難な課題に直面しても、内発的動機が高い人は逃げずに自ら解決策を模索します。
試行錯誤を楽しみながら前向きに取り組み、問題解決能力や忍耐力が養われます。
(例)
・難しいプロジェクトに意欲的に参加
・壁を乗り越える経験ができる
 ミズカラくん
ミズカラくんさらなるやる気を形成し好循環になります。
目標に対する持続的なモチベーション
内発的動機を持つ人は、長期的な目標達成に向けて粘り強く取り組み続ける傾向があります。
自分で設定した目標や価値観に基づくため、途中で諦めにくく、達成感や成長を実感しやすいです。
(例)
・継続的な自己研鑽
・難易度の高い課題への挑戦
メンバーの意欲向上と組織への影響
複数人が内発的動機を高めると、チームの連帯感や協力意識も増し、離職率の低下や職場環境の改善にもつながります。
(例)
・上司の適切な支援
・ポジティブなフィードバック
・メンバーのやる気がアップ
 ミズカラくん
ミズカラくん組織としてのパフォーマンスが向上します。
内発的動機を高めることに関するよくある質問(Q&A)
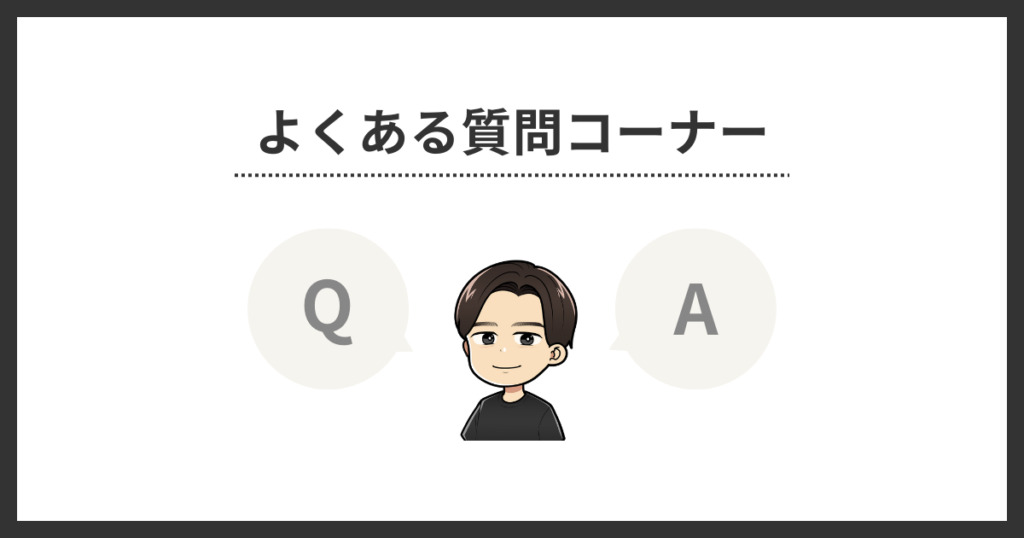
・途中でやる気が切れる場合の対処法を教えてください。
・内発的動機と外発的動機との組み合わせ方はありますか?
・内発的動機が高まらない場合の原因と改善策はありますか?
・内発的動機と自己成長の関係は?
・組織で内発的動機を高める具体的な施策は?
- 途中でやる気が切れる場合の対処法を教えてください。
-
途中でやる気が切れてしまう場合は以下の対処法を参考にしてみましょう。
やる気を持続させるには?- 目標を小さく区切って達成感を積み重ねる
- 休憩やリフレッシュを意識的に取り入れる
- やる気が出ない原因を振り返り、対策を考える
- 周囲のサポートやフィードバックをもらう
- 内発的動機に繋がる好きな要素を見つける工夫をする
- 内発的動機と外発的動機との組み合わせ方はありますか?
-
効果的な組み合わせ方法として以下にまとめました。
1. 段階的アプローチ
- 導入期:外発的動機で行動のきっかけを作る
- 習慣化期:小さな達成感(内発的要素)を重視
- 定着期:内発的動機を主軸に、外発的要素で補完
- 発展期:自律性を保ちながら適度な目標設定
2. 外発的動機の適切な使い方
- 情報的フィードバック:成長が見える評価システム
- 選択肢の提供:複数の報酬から自分で選択
- プロセス重視:結果だけでなく取り組み方も評価
- 予想外の報酬:サプライズ的な認知や感謝
3. 内発的動機を損なわない工夫
- 自律性の確保:やり方や時間を自分で決められる環境
- 意味づけの共有:なぜその仕事が重要かを伝える
- 成長実感の機会:スキルアップを実感できる仕組み
- 関係性の重視:チームとのつながりを大切にする
4. 職場での実践例
- 短期目標:明確な成果指標+達成時の適切な評価
- 中期目標:スキル向上機会+自分なりの工夫の余地
- 長期目標:キャリアビジョン+自律的な働き方
- 日常業務:感謝の表現+自分らしさを発揮できる環境
5. 注意すべきポイント
- 過度な競争は避ける:他者との比較よりも自己成長重視
- 報酬依存を防ぐ:報酬がなくても続けられる仕組み作り
- コントロール感の維持:「やらされている」感を排除
- 個人差への配慮:人それぞれの動機パターンを理解
- 内発的動機が高まらない場合の原因と改善策はありますか?
ミズカラくん
内発的動機が高まらない時ありますよね。
そんな時は以下の改善策を参考にしてみてください。
◾️原因
目標設定が曖昧で自分ごとになっていない◾️改善策
・自分の目標を明確に具体化する
・自分の価値観や関心と結びつける
・実現可能でやりがいのある難易度にする
・進捗の見える化や振り返りの習慣化◾️原因
過度な管理や指示といった裁量の欠如◾️改善策
・自分の得意分野を活かせる環境を見つけて積極的に動く
・指示待ちではなく自ら行動することを考えてみる
・前向きなフィードバックとコミュニケーションを増やす- 内発的動機と自己成長の関係は?
-
内発的動機を高めると、自然と自己成長にも繋がります。
内発的動機と自己成長の関係性- 内発的動機は自己成長への意欲を高め持続的な学習や挑戦を促す
- 自己効力感や達成感がさらなる成長欲求を生み出す好循環となる
- 内発的動機が強い人ほど困難にも粘り強く向き合い能力向上につながる
- 自律的な行動を通じて自己実現やキャリア開発に結びつく
- 組織で内発的動機を高める具体的な施策は?
-
組織内で内発的動機を高めていくと、組織や仕事のレベルアップがみられます。
具体的な施策を以下にまとめました。
具体的な施策- メンバーに裁量や選択の自由を与え自律性を尊重する
- 個々の強みを活かせる仕事や役割を割り当てる
- 目標設定や振り返りの場を設け自発的な行動を促す
- ポジティブなフィードバックや感謝の文化を育てる
- チームビルディングやコミュニケーションを活性化し関係性を深める
まとめ:やらされ感からの脱却!
【内発的動機】を高める6つの具体的ステップ

仕事や学びを続けるうえで、多くの人が「やらされ感」に悩まされがちですが、それを乗り越え自ら動く力につながるのが内発的動機です。
内発的動機は「やりたい」「成長したい」という自分自身の内側から湧き上がる意欲であり、内発的動機を高めることが継続的なやる気や充実感を生み出します。
- 仕事や活動の「意味」や「価値」を自分の中で明確にする
- 自分が決めた目標を設定し段階的な達成体験を積む
- 得意分野や強みを活かせる環境を整える
- 新しい挑戦や自律的な行動の機会を積極的に作る
- ポジティブなフィードバックや感謝の習慣を取り入れる
- 良好な人間関係や信頼関係を築き安心できる環境を整える
上記6つを意識的に実践すると、外部からの強制や報酬に頼らずとも、自律的かつ持続的にやる気が湧き上がります。
 ミズカラくん
ミズカラくん生産性や創造性、満足感の向上にもつながります。
内発的動機を育てることは、個人の幸福感や組織の活力を高めるために重要です。
6つのステップを日々の仕事や生活に取り入れて「やらされ感」からの脱却を目指してください。
以下の動画では
人気著書「自分の変え方」をまるっと解説しています。
内発的動機を高めて、やらされ感から自発的な行動をするには、まず自分自身の考え方や行動を変えることが重要です。
動画を見ると、内発的動機を高められ、想像を超えた自分に出会えます。
■著書『自分の変え方』はこちらから購入できます
↓↓