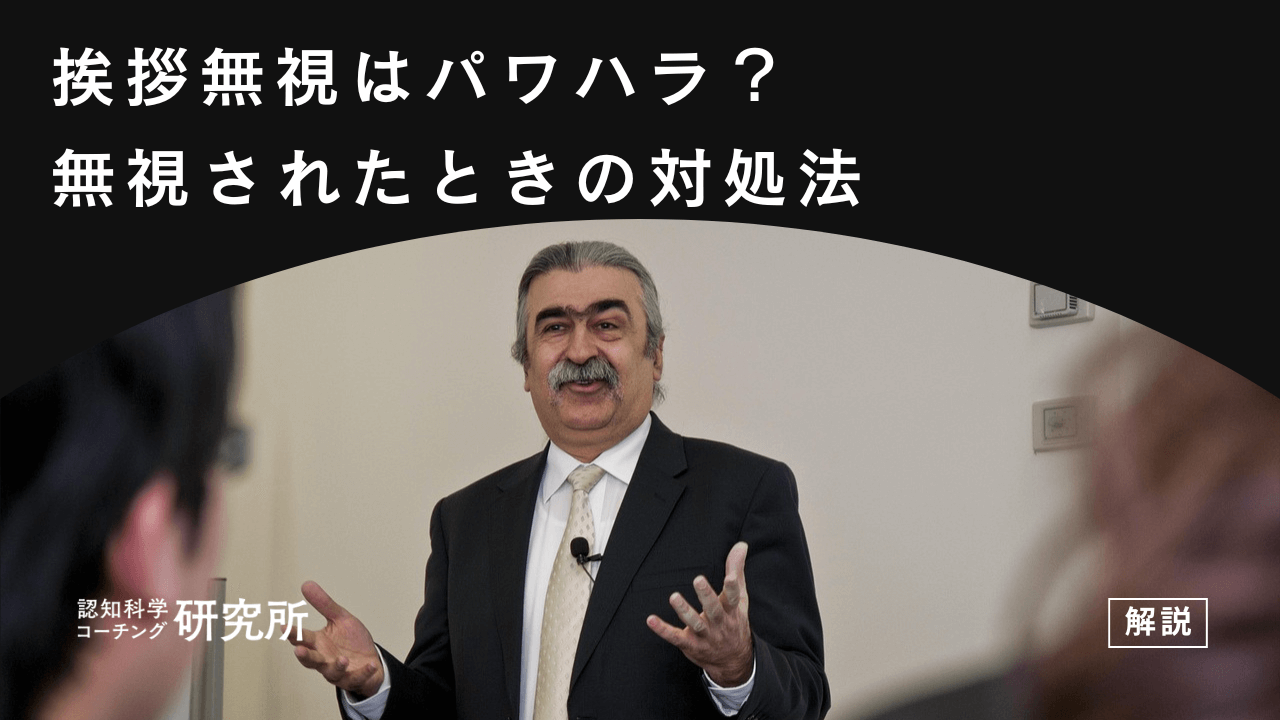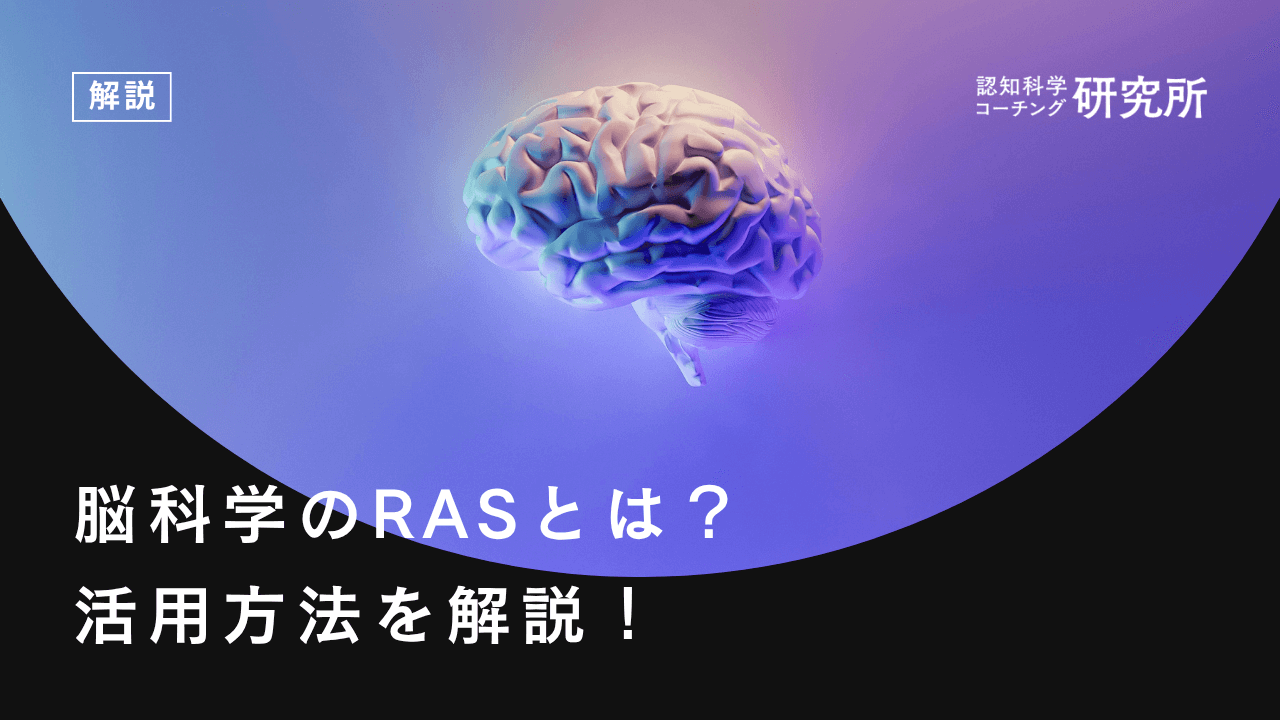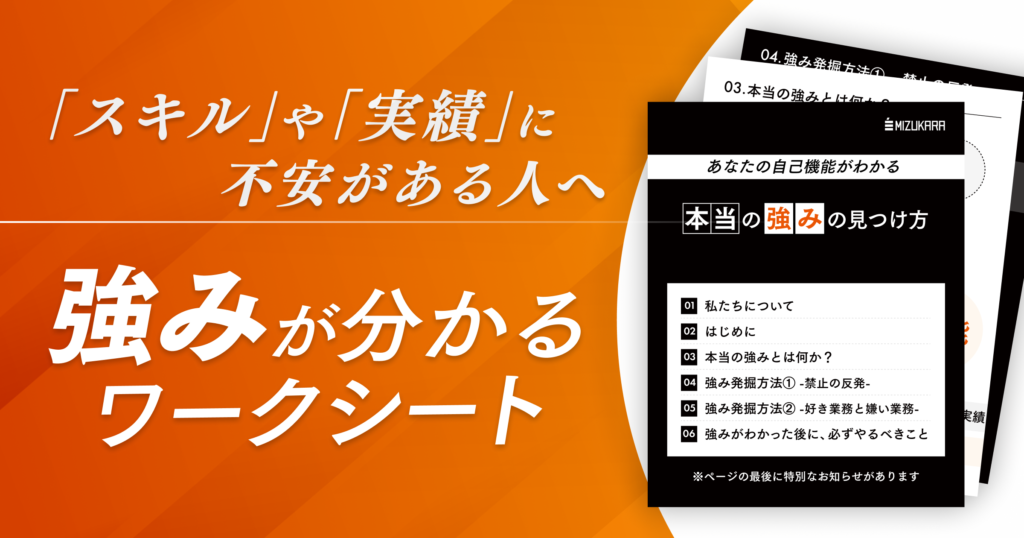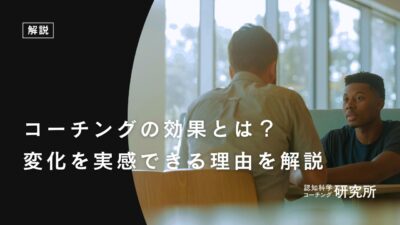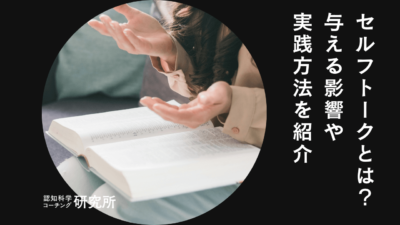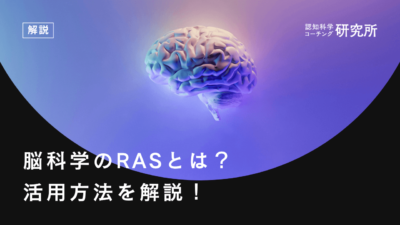自己分析の方法は?
5年後・10年後の理想像はどう描く?
面接や志望動機での伝え方も含めて、キャリアビジョンをわかりやすく解説します。
「やりたいことが分からないまま、働き続けてていいのかな…」
「なんとなく転職したけど、これでよかったんだろうか…」
「将来の自分がまったく想像できない…」
不安や迷いを抱えたまま、目の前の仕事に追われる日々。
でも、自分のキャリアビジョンを描けずに悩んでいるのは、あなただけではありません。
この記事では、自分らしい将来像を見つけるためのキャリアビジョンの作り方をわかりやすく解説します。
読み終えるころには、「この道でいい」と納得できる、自分だけのキャリアの軸が見えてくるはずです。
自分の強みがわからないままでは、キャリアビジョンもぼやけてしまいます。
強みがわかるワークシートでは、過去の経験からあなたの得意なこと・大切にしている価値観を引き出せます。
下記のボタンから無料で、30秒で受け取れるので、キャリアの軸を見つけたい方はぜひご活用ください。
キャリアビジョンの作り方に悩むのは普通のこと

まずは、なぜキャリアビジョンが思いつかないのか、その理由から見ていきましょう。
キャリアビジョンを持てと言われても、すぐに明確な答えを出せる人は多くありません。
「うまく言えない」「何を目指せばいいのかわからない」と感じる人の方が圧倒的に多いはずです。
- 自分の将来像をはっきり描けていないから
- キャリアプランとの違いを理解してないから
- 将来の不安がキャリアの言語化を妨げているから
自分の将来像をはっきり描けていないから
「キャリアビジョンを考えてください」と言われて、戸惑った経験はありませんか。
多くの人は、自分の将来像をはっきり描けていないものです。
今の仕事に精一杯で、先のことまで考える余裕がないからです。
また、やりたいことが明確でないと、「自分にはビジョンがない」と焦ってしまいます。
 ミズカラくん
ミズカラくんでも、思いつかないのはあなたの責任ではありません。
それは、キャリアビジョンを言語化する機会がなかっただけです。
まずは「何をすべきか分からない」と悩む状態から、少しずつ抜け出していけば大丈夫です。
キャリアプランとの違いを理解してないから
混同しやすいのが、「キャリアビジョン」と「キャリアプラン」の違いです。
キャリアビジョンは、将来どうなっていたいかという“理想の姿”です。
一方、キャリアプランは、そのビジョンに向けた“行動計画”を指します。
たとえば「5年後には管理職としてチームを育てたい」がビジョン。
「そのために今の部署でリーダー経験を積む」がプランです。
このように、ビジョンが目的、プランは手段という関係になります。
 ミズカラくん
ミズカラくんまずはビジョンが定まることで、ブレずに行動しやすくなります。
キャリアプランが思いつかないという場合は、下記の記事もご覧ください。

将来の不安がキャリアの言語化を妨げているから
キャリアビジョンを描けない人の多くは、「将来が不安だから描けない」と感じています。
「今の仕事を続けていていいのか」と悩んだり。
「転職したいけど何をしたいかわからない」と迷ったり。
不安があると、人は未来に対して受け身になってしまいます。
しかし、将来を“決める”ことは、コントロール感を取り戻す第一歩でもあります。
大切なのは、「今の延長線上」にこだわらず、理想から考える視点を持つことです。
 ミズカラくん
ミズカラくん不安を前提にしても構いません。
そのうえで、「どうなりたいか」を少しずつ言葉にしていきましょう。
もし、「どうなりたいか」がうまく言葉にできないときは、無理に答えを出さなくても大丈夫。
まずは、自分の感情や願いを丁寧にすくい上げることから始めてみましょう。
未来を整理するための「GOAL設定ワークシート」をご用意しています。
頭の中のモヤモヤを一度、紙の上に広げてみませんか?
キャリアビジョンの作り方|最初にやるべき自己分析
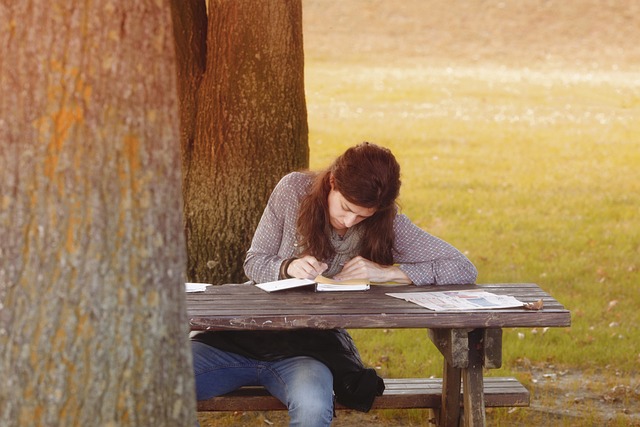
ここでは、自己分析を通じてビジョンの土台をつくる方法を紹介します。
キャリアビジョンを描くには、自分の内側を見つめる作業が欠かせません。
やりたいことを言語化するには、過去の経験や価値観を丁寧に整理することから始まります。
- 自己分析で過去の経験や強みを整理する
- 価値観や理想の働き方を言語化する
- キャリアビジョンの軸を見つける
自己分析で過去の経験や強みを整理する
キャリアビジョンを描くための出発点は、自己分析です。
まずは、これまでの経験を振り返ることから始めましょう。
どんな仕事をしてきたか、どんなときにやりがいを感じたかを書き出してみてください。
 ミズカラくん
ミズカラくん失敗したことも、苦手だったことも、すべてがヒントになります。
「うまくいった理由は?」「なぜそれが楽しかったのか?」と問い直してみましょう。
自分の得意なことや、大切にしている価値観が見えてきます。
強みは、他人と比べるものではなく、自分が自然とやれてきたことの中にあります。
価値観や理想の働き方を言語化する
ビジョンを描くうえで、「どう生きたいか」という価値観は欠かせません。
収入よりもやりがいを重視したい人もいれば、働く場所にこだわりたい人もいます。
まずは「どんな働き方なら心地いいか?」を自由に想像してみてください。
 ミズカラくん
ミズカラくん「チームで働きたい」など、抽象的でも構いません。
次に、それらを「なぜそう思うのか?」と掘り下げていきましょう。
「過去の体験」と「感情」に注目することが、言語化のコツです。
感情が動いた瞬間には、あなたらしさが詰まっています。
キャリアビジョンの軸を見つける
「自分の軸がわからない」と感じたら、問いを使って掘り下げましょう。
- これまでで一番達成感を感じた仕事は何か?
- そのとき、どんな行動をして、どんな評価を受けたか?
- 周囲からよく頼まれることは何か?
- どんな働き方なら続けられそうか?
- 10年後、どんな状態なら「いい人生だった」と思えるか?
こうした問いに答えることで、キャリアビジョンの「軸」が見えてきます。
 ミズカラくん
ミズカラくん軸は1つに絞る必要はありません。
あなたらしい選択ができるよう、複数の視点を持っておくと安心です。
問いに答えていくうちに、自分でも気づいていなかった強みや価値観が浮かび上がってくることがあります。
「これが自分らしさかも」と思える感覚は、キャリアビジョンを描く大きなヒントになります。
そんな自分らしさを引き出す「強みがわかるワークシート」もご用意しています。
一緒に、“あなたの軸”を見つけるきっかけにしてみませんか?
キャリアビジョンの作り方|5年後・10年後の姿を描く

ここでは、将来像を描くためのフレームワークや、現実に落とし込む考え方を紹介します。
キャリアビジョンは「今の延長線」だけでは描けません。
未来の自分をイメージし、少し背伸びをした理想を描くことで、初めて方向性が見えてきます。
- フレームワークで将来像を考える
- 短期・中期・長期に分けたキャリアプランを立てる
- ライフステージとキャリアの両立方法を考える
フレームワークで将来像を考える
将来の自分を描くには、いきなり理想像を考えるのではなく、枠組みを使うのが効果的です。
 ミズカラくん
ミズカラくんたとえば「Will・Can・Must」があります。
- Willは「やりたいこと」
- Canは「できること」
- Mustは「求められること」
この3つの重なり合うところに、自分らしいキャリアのヒントがあります。
やりたいだけでも、できるだけでもなく、「意味のある貢献」が見つかるとブレません。
最初は曖昧でもかまいません。
問いを繰り返しながら、輪郭をはっきりさせていきましょう。
短期・中期・長期に分けたキャリアプランを立てる
将来像を現実にするには、「段階的なプラン」が欠かせません。
たとえば、「5年後にマネージャーになりたい」というビジョンがあるとします。
その場合、3年以内にリーダー経験を積み、1年以内にプロジェクトを任される必要があります。
「長期ビジョン」から逆算して、「中期」「短期」の目標を設定します。
キャリアは一気に飛び越えられるものではありません。
小さな成功を積み重ねて、少しずつ理想に近づく流れを意識しましょう。
 ミズカラくん
ミズカラくん逆算思考を使えば、今やるべきことが明確になります。
ライフステージとキャリアの両立方法を考える
キャリアは、人生そのものと切り離せないテーマです。
結婚、出産、介護など、仕事以外の変化も長期的には大きな影響を与えます。
だからこそ、「仕事だけ」の視点ではなく、「人生全体」の視野で描くことが重要です。
例えば、「30代で子育てと両立したい」「40代で地方に移住したい」
 ミズカラくん
ミズカラくん希望を素直に書き出しましょう。
ライフイベントに合わせて、働き方を変えたり、キャリアを一時的に止めたりする選択もあります。
そうした変化も含めて「しなやかに変化できるビジョン」が、今の時代には求められています。
無理に完璧な未来像を描こうとせず、柔軟に対応できる形にしておくのがコツです。
キャリアビジョンの作り方|具体例・テンプレートで学ぶ
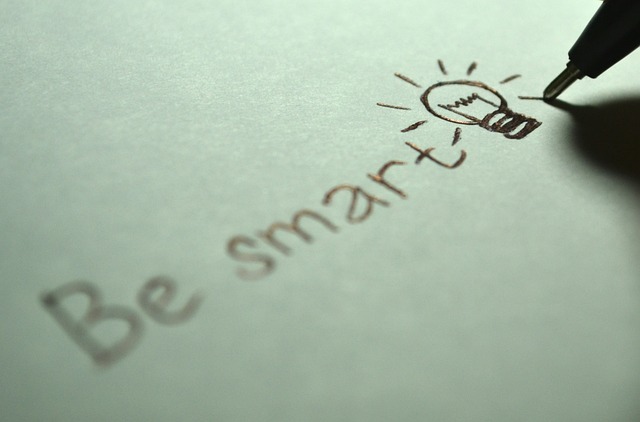
ここでは、職種別の例文や、志望動機・面接への応用法を見ていきましょう。
実際にキャリアビジョンを言葉にしようとすると、「どう書けばいいのか分からない」とつまずくこともあります。
そんなときは、他の人の例やテンプレートを参考にすると、ヒントが得られます。
- 職種別キャリアビジョンの例文(営業・事務・ITなど)
- キャリアビジョンが伝わる志望動機の書き方
- 面接でキャリアビジョンを聞かれたときの答え方
職種別キャリアビジョンの例文(営業・事務・ITなど)
キャリアビジョンを考えるうえで、他の人の例を参考にするのはとても有効です。
- 営業職:「5年後にはチームリーダーとして新規開拓を任される存在になりたい」
- 事務職:「効率化に強いバックオフィス人材として、業務改善をリードできるようになりたい」
- ITエンジニア:「10年後にはプロジェクトマネージャーとして、チームを支える存在を目指したい」
 ミズカラくん
ミズカラくん例文を真似することが目的ではありません。
自分に近い立場の人の言葉をヒントにしながら、自分の言葉に置き換えることが大切です。
具体性があると、面接や社内面談でも説得力が生まれます。
キャリアビジョンが伝わる志望動機の書き方
志望動機を書く際に、「キャリアビジョンとどうつながるか」を意識できると好印象です。
「御社の○○という環境で、△△の経験を積むことが、将来の××というビジョンに直結します」
 ミズカラくん
ミズカラくんこのような構成が有効です。
単に「興味があります」ではなく、「自分の将来と一致している」と伝えることがポイントです。
企業が見ているのは、「この人がうちで成長してくれるかどうか」です。
だからこそ、自分のビジョンを持っている人は、それだけで一目置かれます。
事前に「企業で得られる経験」と「自分の描きたい将来像」をすり合わせておきましょう。
面接でキャリアビジョンを聞かれたときの答え方
面接で「あなたのキャリアビジョンを教えてください」と聞かれることは珍しくありません。
この質問に対しては、「やりたいこと+そのための行動+御社の環境」の3点を盛り込むと効果的です。
「将来的には〇〇の分野で専門性を高め、リーダーとして活躍したいと考えています。そのために、まずは△△の経験を積みたいと考えています。御社では□□のような環境が整っていると感じ、志望しました」
内容に自信がなくても、「考えようとしている姿勢」そのものが評価されます。
 ミズカラくん
ミズカラくん曖昧でも構わないので、言葉にしてみることが一歩目です。
伝える練習をするほど、自分自身のビジョンもよりクリアになっていきます。
キャリアビジョンの作り方|定期的な見直しが鍵

ここでは、振り返りのタイミングやアクションプランの立て方について具体的に紹介します。
キャリアは、常に変化し続けるものです。
だからこそ、一度決めたビジョンも、定期的に見直すことが欠かせません。
- 経験や環境の変化に対応する
- 「期限」を設ける
- 社内面談や転職時には最新のキャリアビジョンを考える
経験や環境の変化に対応する
キャリアビジョンは、一度作って終わりではありません。
人の価値観や興味は、経験や環境の変化とともに少しずつ変わっていきます。
たとえば、入社当初は「専門性を高めたい」と思っていた。
でも、3年後には「マネジメントにも挑戦したい」と感じることもあります。
柔軟に変えていける人のほうが、成長につながるキャリアを築いています。
「期限」を設ける
 ミズカラくん
ミズカラくんキャリアビジョンを動かすには、アクションプランが必要です。
アクションプランとは、「いつ・何を・どの順番でやるか」を整理した行動計画のことです。
「理想」に近づくための小さな一歩でも、期限を設けることで実行力が上がります。
- 資格取得などの進捗確認
- 部署内での新しい挑戦の棚卸し
- 理想のキャリア像とのズレの確認
社内面談や転職時には最新のキャリアビジョンを考える
キャリアシートは、自分のキャリアを整理し、相手に伝えるために有効です。
 ミズカラくん
ミズカラくん内容は以下の3点でまとめると効果的です。
- これまでの経験
- 今後やりたいこと
- その理由
面談時にキャリアシートを用意しておけば、主体性のある印象を与えることができます。
「未来の自分に向けた地図」として、キャリアシートは何度でも書き直して使えます。
キャリアビジョンの作り方に関するよくある質問
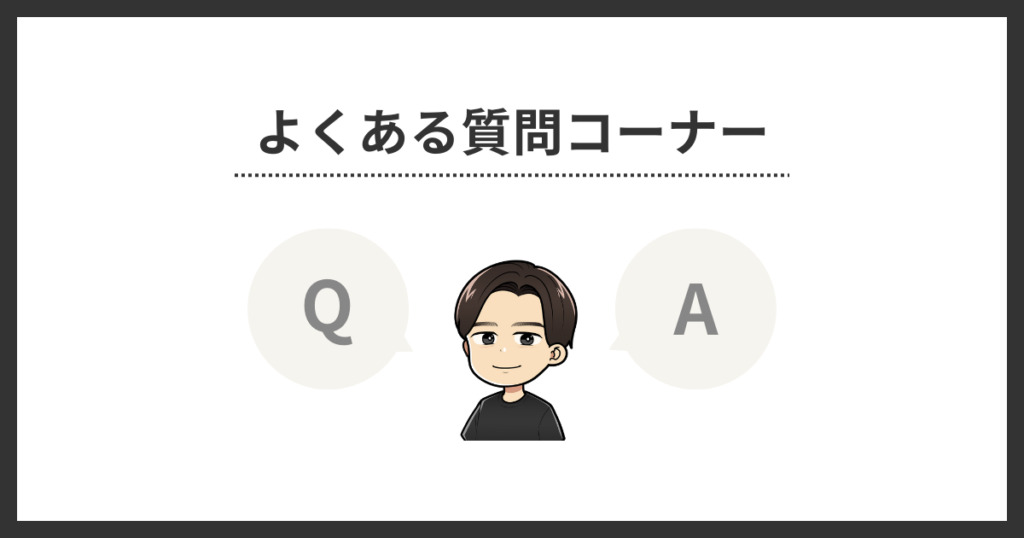
キャリアビジョンの作り方に関するよくある質問に回答します。
- キャリアビジョンが思いつかないときはどうすればいい?
- 曖昧なキャリアビジョンでも面接で使える?
- キャリアビジョンは途中で変わっても大丈夫?
まとめ:キャリアビジョンの作り方で自分の未来に自信を持てるように

キャリアビジョンは、最初から完璧に描けるものではありません。
でも、自分の過去を振り返り、価値観を整理し、将来の理想像を言葉にすることで、少しずつ形になっていきます。
「思いつかない」という悩みは、「真剣に考えようとしている証拠」です。
 ミズカラくん
ミズカラくん焦らず、自分のペースで進めていきましょう。
ビジョンを持つことで、選択に迷ったときの指針ができます。
また、行動に意味や目的が生まれ、日々のモチベーションにもつながります。
まずは「今の自分」を知るところから、キャリアの旅は始まります。
一歩ずつでも行動を積み重ねれば、未来はきっと言葉にできるようになります。
本当の自分と向き合うのが怖い方は、以下の動画をご覧ください。
弱い自分を克服した人の体験談をまとめています。