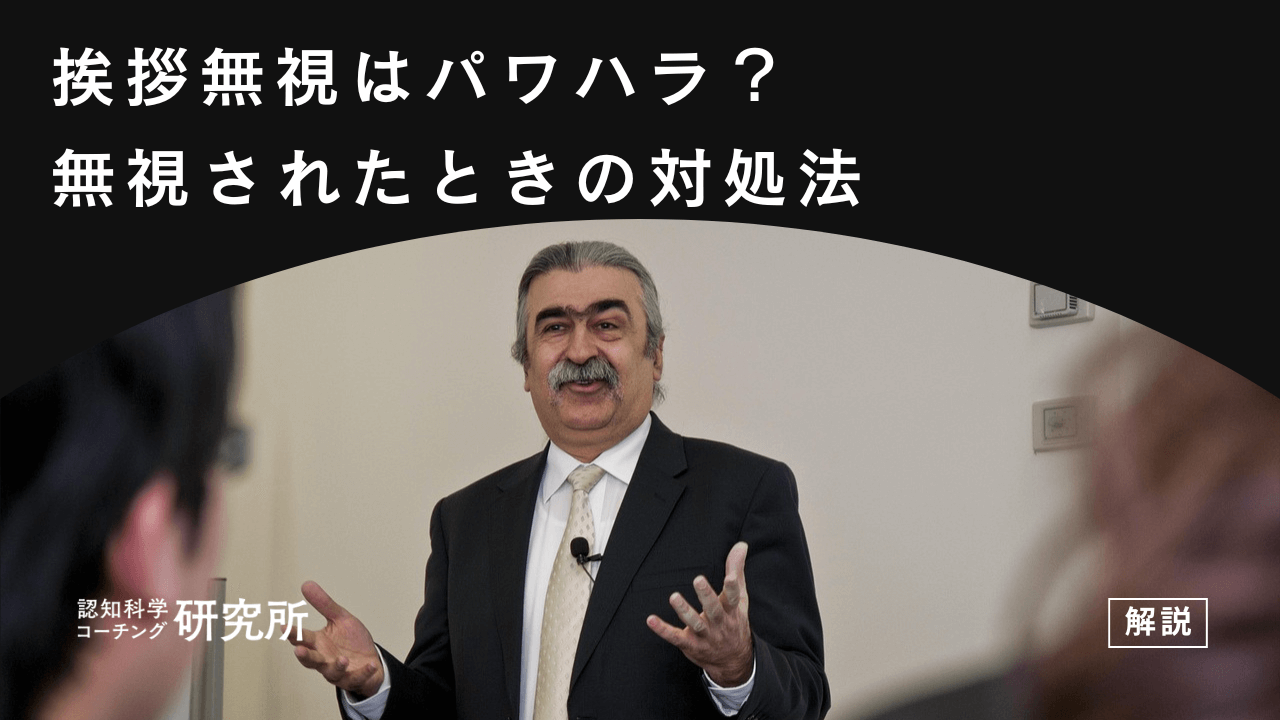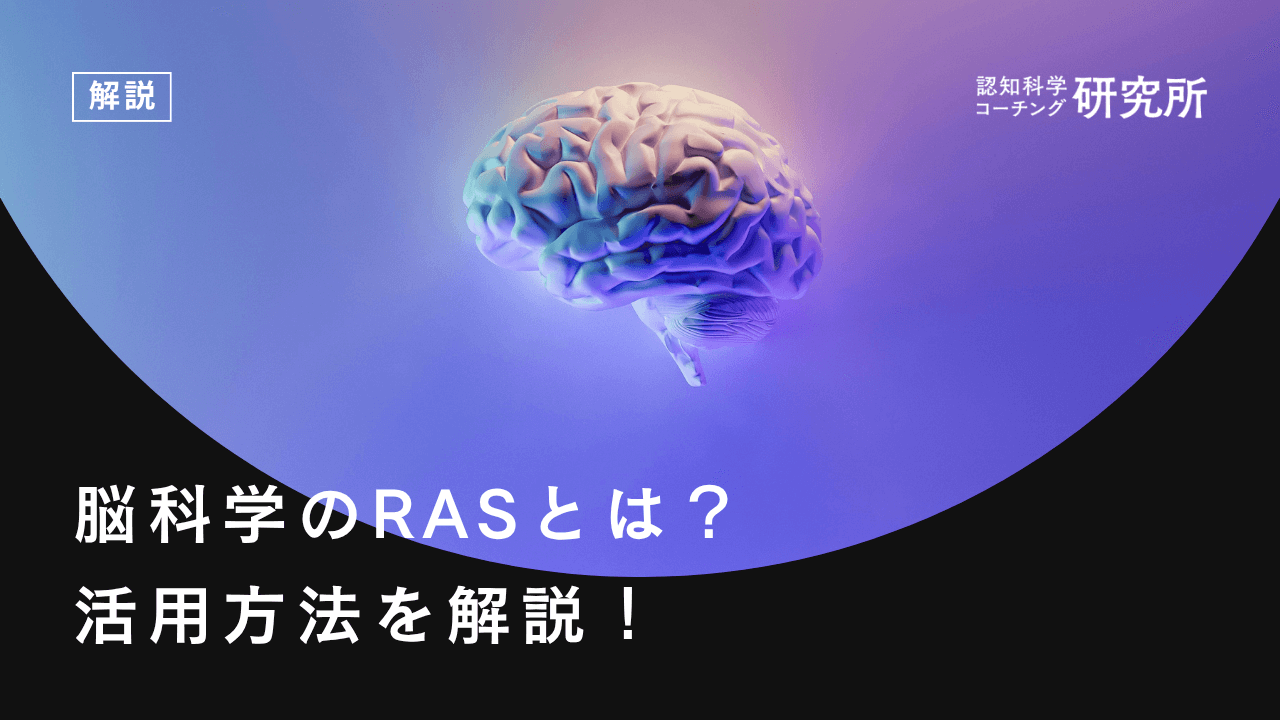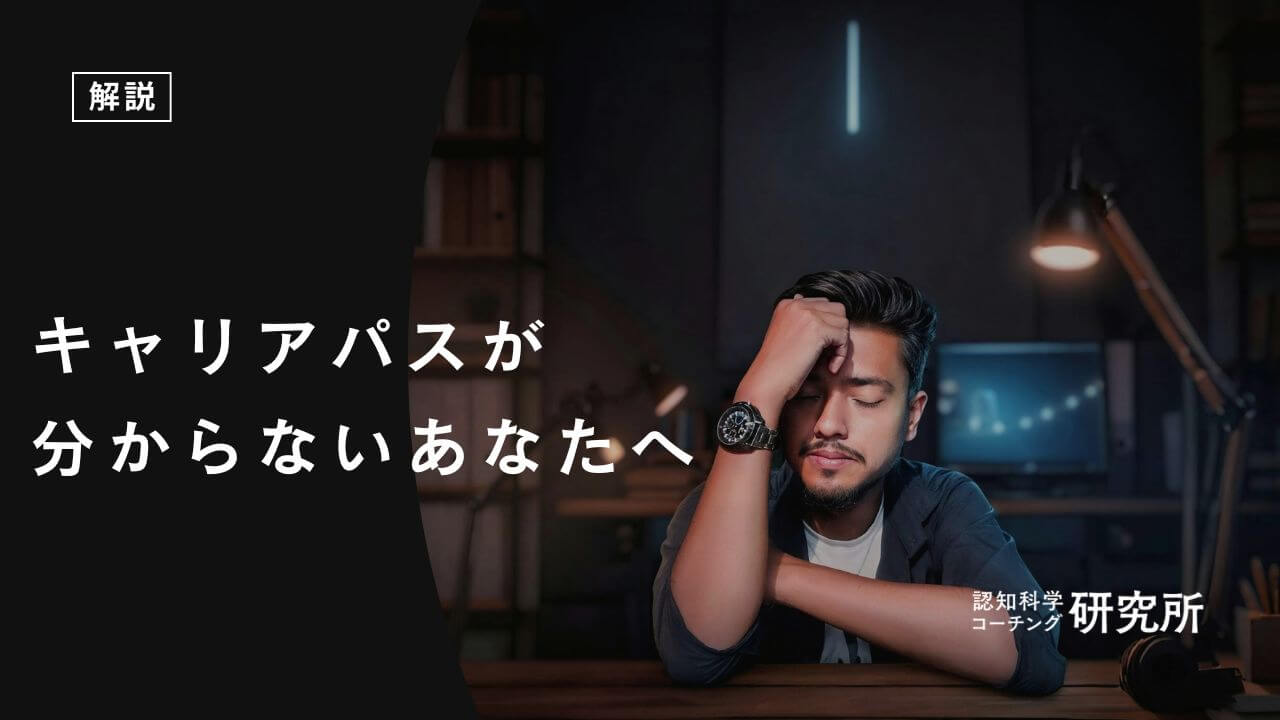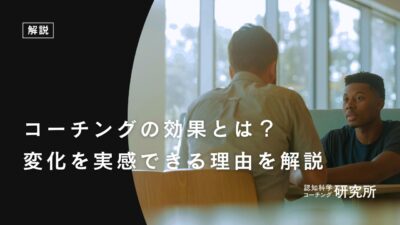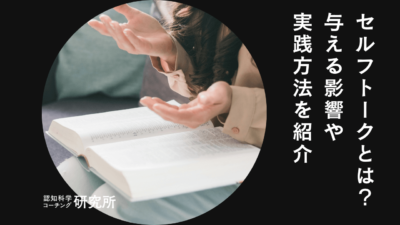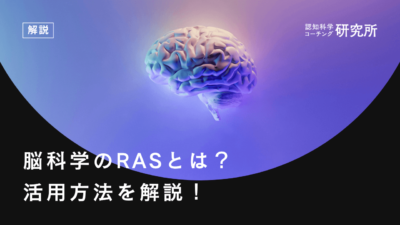「キャリアパスってそもそも何?」
「キャリアパスが分からない、必要な理由は?」
「キャリアパス通りに行動しているけど今のままで良いのか?」
この記事ではキャリアパスが分からない人や、今のキャリアパスで本当に良いのか不安を解消できるよう解説しています。
「キャリアパスって何?どうやって考えればいいの?」
「今の仕事の先に、何があるのか分からない…」
「周りは着実に進んでいるのに、自分だけ迷っている気がする」
こんな風に、キャリアパスが分からないと感じたことはありませんか?
この記事では、15,000名以上のキャリア悩みを解消してきたキャリアコーチング専門家が、キャリアパスでの「将来が見えない」という不安の正体と、そこから抜け出すための考え方・行動のヒントを、分かりやすく解説します。
この記事を読むと、キャリアパスとは何か?という基礎的な理解が深まり、自己分析や一歩踏み出す行動と自信に繋がります。
キャリアパスが分からない人は、まずはキャリアパスを理解することと、今の自分の状態を客観的に整理し「GOAL設定」をすることが大切です。
GOAL設定ワークシートを活用すれば、質問に答えるだけでキャリアパスについて理解し、理想の未来が明確になります。
以下のボタンから、たった30秒で無料で受け取れるので、ぜひ試してみてください!
キャリアパスとは?

ここでは、キャリアパスの定義のほか「キャリアプラン・キャリアデザイン・キャリアビジョン…」などの、似た名目との違いを解説します。
- キャリアパスの定義
- キャリアプランとの違い
- キャリアデザインとの違い
- キャリアビジョンとの違い
- キャリアアップとの違い
キャリアパスの定義
キャリアパスとは、英語で「キャリア(Career)=経歴・職歴」、「パス(Path)=道」です。
ある職業人生において「どのような道筋」でキャリアを築いていくかを示した設計図のようなものです。
また、キャリアパスは主に企業側が社員に提示するもので、近年は人事制度の一つとして「キャリアパス制度」を設ける企業が増えています。
ポジション・役割・専門領域などの選択肢を時系列で描くことで、自分の成長経路が見えてきます。
キャリアプランとの違い
キャリアプランは「具体的にいつまでに何をするか」を決めるもので、短期・中期的な目標設定にフォーカスします。
キャリアパスが大筋の“構造”とすると、プランはその“実行計画”です。
キャリアデザインとの違い
キャリアデザインは自分自身の価値観・ライフスタイル・働き方の好みを踏まえて、人生全体をいかに設計するかという概念です。
キャリアデザインは、人生全体の設計を補完する“職業的な道筋”の具体化と捉えて良いでしょう。
キャリアビジョンとの違い
キャリアビジョンは「将来どんな自分で在りたいか」を描く心象的なイメージです。
ビジョンがあなたの山頂なら、キャリアパスはそこへ続くルート図のような役割を持ちます。
キャリアアップとの違い
キャリアアップは「より高い役職やスキルを獲得する」という成果や進歩の局面を指します。
いわばキャリアパス上の“マイルストーン”であり、通過点の一つです。
なぜ多くの人が「キャリアパスが分からない」と感じるのか?

キャリアパスが分からないと感じる理由についてみていきます。
- キャリアパスは“見えづらいもの”だから
- 社会の変化が早すぎて、未来を描きづらい
- 会社にキャリアのモデルが用意されていない
- 自分の“やりたいこと”が分からない
- 他人と比べてしまい、余計に迷ってしまう
キャリアパスは“見えづらいもの”だから
キャリアパスは、目に見えない未来や抽象的な道筋を自分で描く必要がある点で、多くの人がイメージを持ちにくく感じます。
特に初期キャリアほど、構造や道(パス)がぼやけがちです。
まずは「今できること」「理想のイメージ」を紙に書き出し、簡単なキャリアマップを作ってみましょう。
 ミズカラくん
ミズカラくん“曖昧さを整理する”ことが、見えない道を形にする第一歩!
「キャリアパスが分からない」と感じている方の多くは、今の自分の立ち位置を見極めることが、未来を描く第一歩になります。
GOAL設定ワークシートを使えば、質問に答えるだけで自分の理想像と現在地を整理でき、行動の方向性が見えてきます。
以下のボタンから30秒で無料で受け取れますので、迷っている方はぜひ今この瞬間から一歩踏み出してみてください。
社会の変化が早すぎて、未来を描きづらい
テクノロジーの進化や働き方の多様化により、数年前にあった「スタンダード」が通用しにくくなり、不確実さがキャリアパス設計をより難しくしています。
変化を前提に「短期ゴール+柔軟な中期プラン」を意識しましょう。
3年後の完璧な未来を描く必要はありません。
半年〜1年単位の「仮のゴール」を設定して、実践しながら見直すことが鍵です。
会社にキャリアのモデルが用意されていない
特に中小企業やベンチャーでは、明確な職能体系や昇進モデルが整備されていない場合が多く「次に何を目指せば良いか」が見えづらい環境です。
会社の枠にとらわれず、業界全体や他社のキャリア事例をリサーチしましょう。
 ミズカラくん
ミズカラくん転職サイトやOB訪問を活用し、キャリアの選択肢を広げよう!
自分の“やりたいこと”が分からない
やりたいことが曖昧だと「その先へ進むべき道」も定まりません。
自分の価値観や興味、無自覚な欲求に気づくことが、キャリアパスを描く第一歩になります。
まずは、自己分析のワークを取り入れましょう。
- 「これまでで一番楽しかった仕事は?」
- 「どんな時に時間を忘れて集中した?」
- 「嫌だった仕事は?」
上記のような問いに答えることで、自分の価値観やモチベーションの核が見えてきます。
他人と比べてしまい、余計に迷ってしまう
SNSや周囲の成功体験と比較すると、自分の道が相対的に“足りない”ように感じて苦しくなります。
比べる対象を「他人」ではなく「過去の自分」に変えてみましょう。
 ミズカラくん
ミズカラくんキャリアの正解は一つではありません。
他人のパスをなぞるのではなく、自分が大切にしたい価値観を起点にしたキャリア設計を意識してください。
「キャリアパスが分からない」状態から抜け出すための6ステップ

「キャリアパスが分からない」状態から抜け出すためのステップを紹介します。
- 「分からない」ことを受け入れる
- 自分の価値観とモチベーションの棚卸し
- 働き方・職種・業界の選択肢を知る(情報収集)
- ロールモデルやメンターに学ぶ
- まず“小さな実践”から動き出す
- 定期的に立ち止まり、見直す習慣を持つ
1、「分からない」ことを受け入れる
まず最初に大切なのは「分からない」ことを否定せず、自然な状態として受け入れることです。
変化の激しい現代において、誰しもがキャリアに迷い、立ち止まる瞬間を経験しています。
むしろ「分からない」と気づけたことが、キャリア探索の始まりでもあります。
完璧な道筋を描くことよりも、まずは曖昧さをそのままに認めましょう。
キャリアパスが分からないとき、一番つらいのは「何をどう考えればいいのか分からない」という“整理のできなさ”ではないでしょうか。
今の自分を客観的に見つめ直し、GOAL設定ワークシートを使い「どんな未来を目指したいのか」考えていきましょう。
以下のボタンから、たった30秒で無料で受け取れますので、ぜひ気軽に試してみてください。
2、自分の価値観とモチベーションの棚卸し
キャリアパスが分からないと感じる一番の理由は「自分が何を大切にしているのか」「何にやりがいを感じるか」が整理できていないことにあります。
ゴールを設定する前に、自分の価値観を言語化することが第一歩です。
価値観やモチベーションの棚卸しをするには、次の3つの質問に答えてみましょう。
- どんな時に仕事のやりがいを強く感じるか?
- これまでの仕事で「楽しい」と思えた瞬間はどんな時か?
- お金、やりがい、自由な時間、どれを最優先したいか?
これらに答えることで、自分が本当に大切にしたいものが見えてきます。
この棚卸しをせずに転職やキャリアチェンジをすると、「思っていたのと違う」と後悔しやすくなります。
逆に、価値観が明確になると、どんな選択もブレない自分軸で判断できるようになります。
3、働き方・職種・業界の選択肢を知る(情報収集)
「キャリアパスが分からない」の背景には、情報不足もあります。
今の仕事や業界だけでなく、広い視野で職種や働き方を調べてみましょう。
- 副業
- リモートワーク
- スタートアップ
- NPO
- 書籍
- キャリアイベント
- 転職サイト
- SNS
働き方の種類を知ることや情報を収集することで、キャリアパスの幅が大きく広がります。
4、ロールモデルやメンターに学ぶ
 ミズカラくん
ミズカラくん自分一人で将来の道を見つけるのは、時に孤独です。
だからこそ、自分にとっての“少し先を歩く誰か”を見つけましょう。
ロールモデルやメンターの存在は、自分の可能性を照らしてくれる貴重なヒントになります。
なりたい誰かの存在を見つけたら、その人が「どんな道を進んできたのか」「どう乗り越えてきたのか」を知ることで、キャリアパス形成の羅針盤となります。
5、まず“小さな実践”から動き出す
考えるだけでは、キャリアパスは具体化しません。
大きな決断よりも「気になる分野の勉強を始めてみる」「副業にトライする」「社内で別プロジェクトに関わる」など、小さな実践が大切です。
実際に行動することで、自分にとっての“しっくりくる感覚”が見えてきます。
6、定期的に立ち止まり、見直す習慣を持つ
 ミズカラくん
ミズカラくんキャリアパスは一度決めたら終わりではありません。
定期的に振り返り、必要があれば方向修正する柔軟さが求められます。
月に一度、自分の現在地と進みたい方向を確認するだけでも、迷いにくくなります。
「進みながら考える」ための習慣化が、キャリアの不確実性を味方につける鍵です。
キャリアパスが分からない人にこそ、キャリアパスが“必要”な理由

キャリアパスが分からない人こそ「キャリアパス」が必要な理由をまとめました。
- “分からない”まま働き続けると、日々が「消費」になるから
- 「なんとなく」で選び続けると、自分の軸が失われていくから
- “見える地図”があると、不安や迷いが整理されるから
- 変化の時代を“自分らしく生きる”ための足場になるから
- キャリアパスがあると、日々の選択が“意味ある一歩”になるから
“分からない”まま働き続けると、日々が「消費」になるから
目標や方向性がない状態で働き続けると、時間やエネルギーを“消費”している感覚に陥りやすくなります。
「何のために働いているのか」が見えなければ、日々の仕事もただの作業になります。
 ミズカラくん
ミズカラくん仕事へのやりがいって大切。
「なんとなく」で選び続けると、自分の軸が失われていくから
 ミズカラくん
ミズカラくん上司に言われた通りに動く、流れに身を任せる…。
そんな日々が続くと「本当はどうしたかったのか」という自分の意思が分からなくなっていきます。
キャリアパスを考えることは、「選ぶ」ことの主体性を取り戻すプロセスでもあります。
“見える地図”があると、不安や迷いが整理されるから
キャリアパスは未来を正確に予測するものではありませんが、進むべき方向性を描く「地図」のようなものです。
道に迷ったときに戻れる地図があることで、感情的な不安も整理しやすくなります。
変化の時代を“自分らしく生きる”ための足場になるから
正解のない時代には「自分はどうありたいか」という軸がより重要になります。
キャリアパスを持つと、他人の期待や世間の常識に振り回されません。
 ミズカラくん
ミズカラくん“自分らしい選択”が可能になります。
キャリアパスがあると、日々の選択が“意味ある一歩”になるから
毎日の仕事や学びが、将来へつながっているという感覚は、働く意欲や継続の原動力になります。
キャリアパスがあると「今ここで頑張る理由」が明確になり、小さな行動も“意味ある一歩”へと変わっていきます。
「キャリアパスが見えない」人が退職後・退職前に取り組むべき解決ステップ
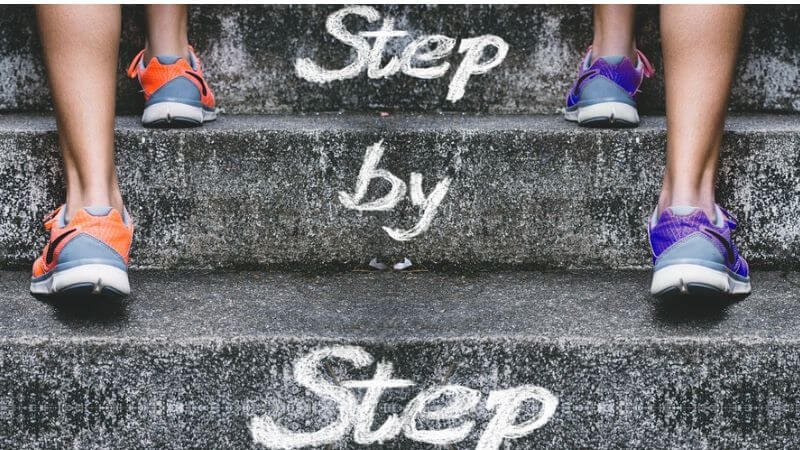
キャリアパスが分からない人が、退職後・退職前に取り組むべきステップをお伝えします。
- 「なぜ分からないのか」を掘り下げてみる
- 「外的キャリア」ではなく「内的キャリア」を見直す
- 「退職=解決」ではなく、「選択肢のひとつ」として捉える
- 一人で抱え込まず、対話の場を持つ(プロとのコーチングなど)
- 小さく始めてみる(副業/発信/学び直し)
「なぜ分からないのか」を掘り下げてみる
キャリアパスが見えない…その感覚の正体は「選択肢の不在」ではなく、「選び方が分からない」ことにあるかもしれません。
何が不安なのか?何に違和感を覚えているのか?自分の“分からなさ”をさらに分解してみることで、原因や手がかりが浮かび上がってきます。
 ミズカラくん
ミズカラくん焦らず、自問自答する時間を持つことが出発点です。
「外的キャリア」ではなく「内的キャリア」を見直す
多くの人が「職位」や「収入」など、外から評価される“外的キャリア”に囚われがちですが、本当に大切なのは「自分がどんな価値を感じながら働きたいか」という“内的キャリア”の設計です。
退職前後こそ、自分の喜び・関心・貢献したい対象といった“内側の軸”に光を当てるべきタイミングです。
「退職=解決」ではなく、「選択肢のひとつ」として捉える
 ミズカラくん
ミズカラくん「辞めたい」は現状から抜け出したいというサイン。
退職はあくまで手段のひとつであり、必ずしも最善策とは限りません。
異動や業務変更、副業スタートなど「変える方法」は他にもあります。
退職が“逃げ”ではなく“選択”になるためには、感情だけでなく視野を広げて状況を見つめ直すことが大切です。
一人で抱え込まず、対話の場を持つ(プロとのコーチングなど)
キャリアの迷いは、頭の中で堂々巡りになりがちです。
そんな時は、信頼できる他者に話すことが突破口になります。
特に、キャリアコーチやキャリアカウンセラーといったプロとの対話は、自分でも気づけなかった視点や資質を浮き彫りにしてくれます。
対話の中で「言葉にすること」自体が、キャリアの輪郭をつくり出します。
小さく始めてみる(副業/発信/学び直し)
 ミズカラくん
ミズカラくんいきなり大きく人生を変える必要はありません。
「ブログを書いてみる」「副業に挑戦してみる」「講座を受けてみる」など、小さな行動を通じてキャリアの“仮説”を検証していくことが有効です。
小さく動くことで、自分の感覚や好奇心が再び目覚めていきます。
【キャリアパスが分からない人向け】将来の目標が見えやすくなる具体例

キャリアパスが“分からない”理由の一つは、具体的なイメージが持てないからです。
ここでは代表的な職種のモデルケースを紹介します。
- 総合職のキャリアパス(例:大手メーカー・総合商社)
- エンジニア職のキャリアパス(例:IT企業・開発部門)
- 営業職のキャリアパス(例:人材・広告・保険業界)
- 管理部門(経理・人事・総務など)のキャリアパス
- 複線型キャリアパスの例(例:ユニリーバ、パナソニックなど)
総合職のキャリアパス(例:大手メーカー・総合商社)
- 入社〜数年:営業・企画・生産管理などをローテーション
- 中堅〜10年目:部門のリーダー候補に抜擢される
- 以降:管理職/専門職(技術・法務など)/海外赴任の道へ分岐
- 特徴:幅広い部署経験が活かせる“ゼネラリスト型”キャリア
エンジニア職のキャリアパス(例:IT企業・開発部門)
- 初期:プログラミングや実装を中心とした実務経験
- 中堅:プロジェクトリーダー、アーキテクトへの昇格
- 以降:技術専門職(フェロー)、マネジメント(部長・CTO)などに分岐
- 特徴:スキル深化とマネジメントのどちらにも伸びる“二軸型”キャリア
営業職のキャリアパス(例:人材・広告・保険業界)
- 初期:法人営業や個人営業に従事し、成果を上げる
- 中堅:チームリーダー、営業企画職へのキャリアシフト
- 以降:支店長・エリアマネージャー/他職種転換(マーケ等)
- 特徴:成果を起点に多職種へ展開できる“実績
管理部門(経理・人事・総務など)のキャリアパス
- 初期:経費処理・採用事務などのオペレーション業務
- 中堅:制度設計や分析、内部統制など戦略的業務へ
- 以降:部門マネージャー/CxO候補/専門特化型(社労士・会計士など)
- 特徴:業務の深さと制度
複線型キャリアパスの例(例:ユニリーバ、パナソニックなど)
- 初期:キャリアの土台づくりと適性の発見
- 中堅:トラック選択と専門性・マネジメント力の育成
- マネジメントトラック:チームやプロジェクトのマネジメントを担い、部下の育成や戦略実行の役割を担います。組織運営・人材開発・経営的視点が求められる
- スペシャリストトラック:技術・法務・ブランド戦略など、特定の専門分野で知見を深め、社内外で高い価値
- 以降:キャリアの深化と社内外での影響力拡大
- 特徴:管理職にならなくても専門領域でキャリアアップが可能
キャリアパスが分からないに関するよくある質問(FAQ)
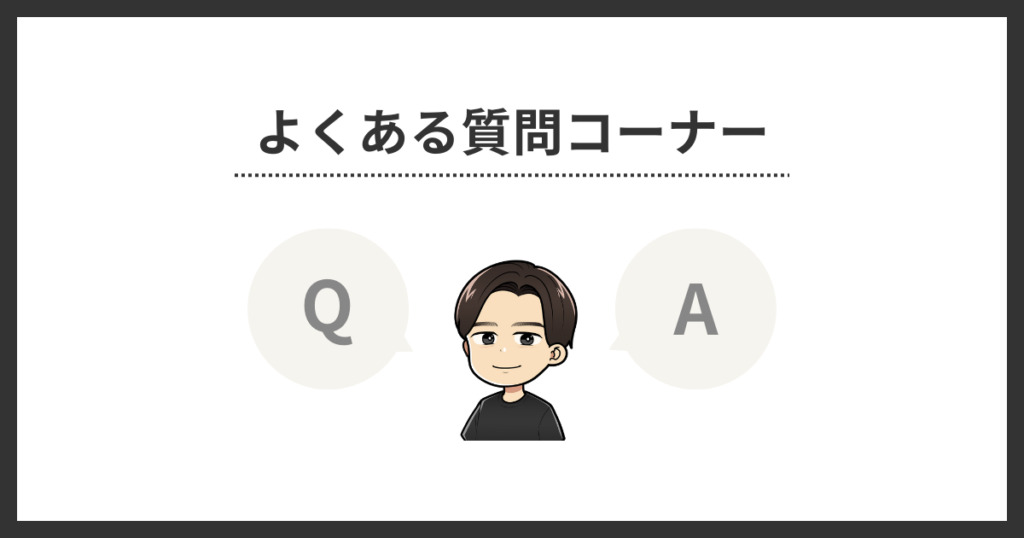
以下では、キャリアパスが分からない人向けに良くある質問を紹介します。
- キャリアパスは会社から出してもらうものなの?
- キャリアパスって、必ず明確に決めておかないといけませんか?
- 他の人はどうやってキャリアパスを見つけているのでしょうか?
- キャリアパスが分からないと、転職してもうまくいかない気がします…
- 今の会社にキャリアパスがなくて不安です。どうすれば?
- キャリアパスを考えると、逆に焦ってしまいます…
- キャリアパスは会社から出してもらうものなの?
-
会社が提供する「モデルキャリアパス」は、あくまで“参考のひとつ”です。
本来のキャリアパスは、自分自身の価値観や人生の優先順位をもとに、主体的に描くものです。
もちろん、企業が用意する成長ルートや制度を活用することも大切ですが、「与えられるもの」として待つのではありません。
 ミズカラくん
ミズカラくん「選び、組み立てるもの」として向き合うことが重要です。
- キャリアパスって、必ず明確に決めておかないといけませんか?
-
いいえ、明確である必要はありません。
むしろ、“決めすぎる”ことがキャリアの可能性を狭めてしまうこともあります。
重要なのは「方向性」と「仮の仮説」を持って動きながら、柔軟に軌道修正すること。
未来は変化しますし、自分自身も変わっていきます。
 ミズカラくん
ミズカラくんキャリアパスは“書き換え可能な地図”と捉えましょう。
- 他の人はどうやってキャリアパスを見つけているのでしょうか?
-
多くの人は、最初から明確な答えを持っているわけではありません。
試行錯誤しながら、経験を通して少しずつ自分なりのパターンや方向性を見出していくものです。
ポイントは「行動すること」「対話すること」「振り返ること」
 ミズカラくん
ミズカラくんそのサイクルの中で、自分の道が輪郭を持ち始めます。
- キャリアパスが分からないと、転職してもうまくいかない気がします…
 ミズカラくん
ミズカラくんその不安はとても自然です。
ただ、転職がうまくいくかどうかは「キャリアパスが明確か」よりも「自分にとっての判断基準があるか」によるところが大きいです。
自分の大切にしたい価値観や、これまでの経験から見えてきた強みなどをもとに、転職先を“選ぶ視点”が育っていれば、たとえ道が未完成でも納得感ある選択ができます。
- 今の会社にキャリアパスがなくて不安です。どうすれば?
-
会社に明確なキャリアモデルがない場合、自ら情報収集をしたり、他社の制度やロールモデルに学んだりすることが大切です。
また、副業やスキルアップ講座など、社外での選択肢を育てておくのも大きな安心材料になります。
 ミズカラくん
ミズカラくん社内外に目を向け“しっくりくる成長の形”を仮設定してみよう。
- キャリアパスを考えると、逆に焦ってしまいます…
-
キャリアについて考えようとすると「早く決めなきゃ」「正しい選択をしなきゃ」と焦る方は少なくありません。
でも、キャリアパスは「正解を探す」ものではなく「問い続けていく」もの。
今わからないのは、あなたがまだ“深く考えようとしている証拠”です。
 ミズカラくん
ミズカラくん答えよりも「問いを持ち続ける力」が未来を照らします。
「キャリアパスが分からない」あなたへ——迷いを抜け出すための考え方6ステップ
「キャリアパスが分からない」という感覚は、多くの人が人生のある時期に抱える内なる問いです。
未来が見えづらくなったときこそ、焦らず、自分の内側と対話することが大切です。
以下の9つのステップは、そんな迷いを抜け出すための“地図の描き方”です。
- 「分からない」ことを受け入れる
- 価値観とモチベーションの棚卸しをする
- 職種・働き方の情報を集める
- ロールモデルやメンターに触れる
- 小さな行動から始める
- 定期的に振り返る
- 「内的キャリア」を意識する
- 一人で抱えず対話する
- “選択肢”としての退職を冷静に検討する
 ミズカラくん
ミズカラくんキャリアは“決めるもの”ではなく「育てていくもの」
誰かと比べず、あなた自身の「しっくりくる道」を、少しずつ見つけていきましょう。
以下の動画では、キャリアコーチングを受けた後、自分のGOALを見つけライフスタイルも月収も大きく変化した方のインタビューを見ることができます。