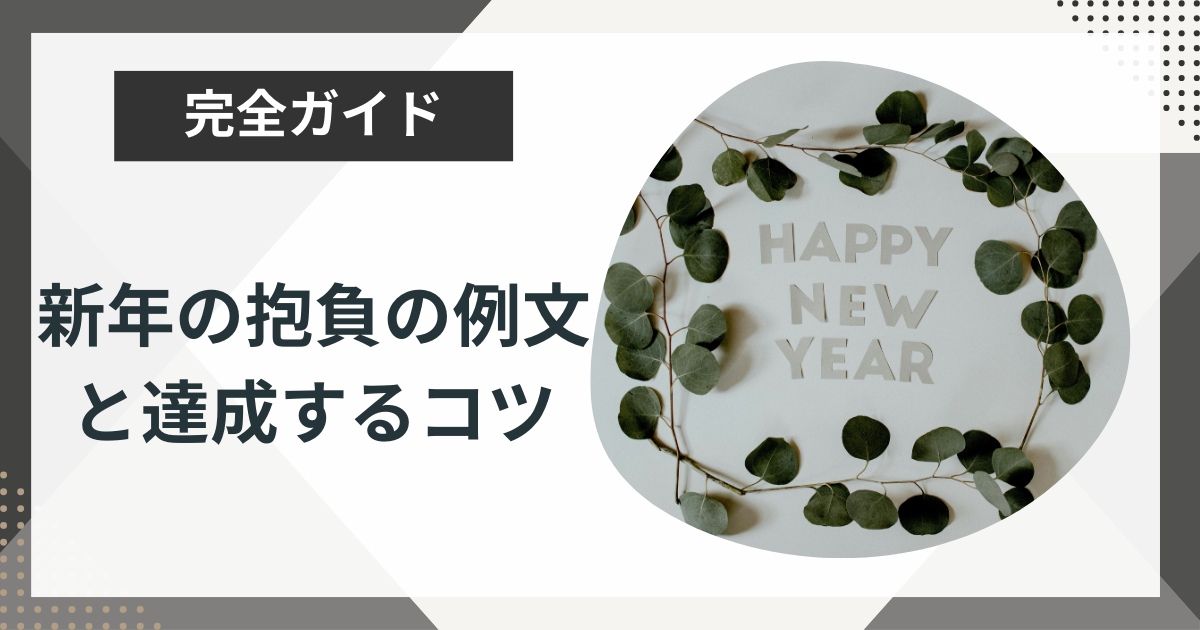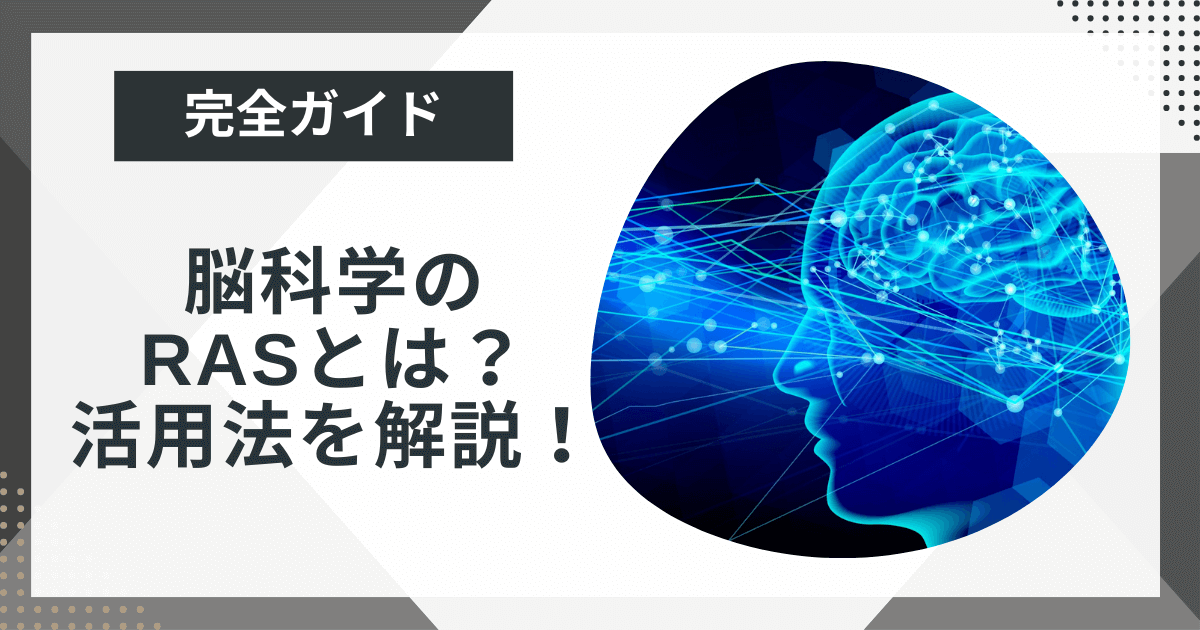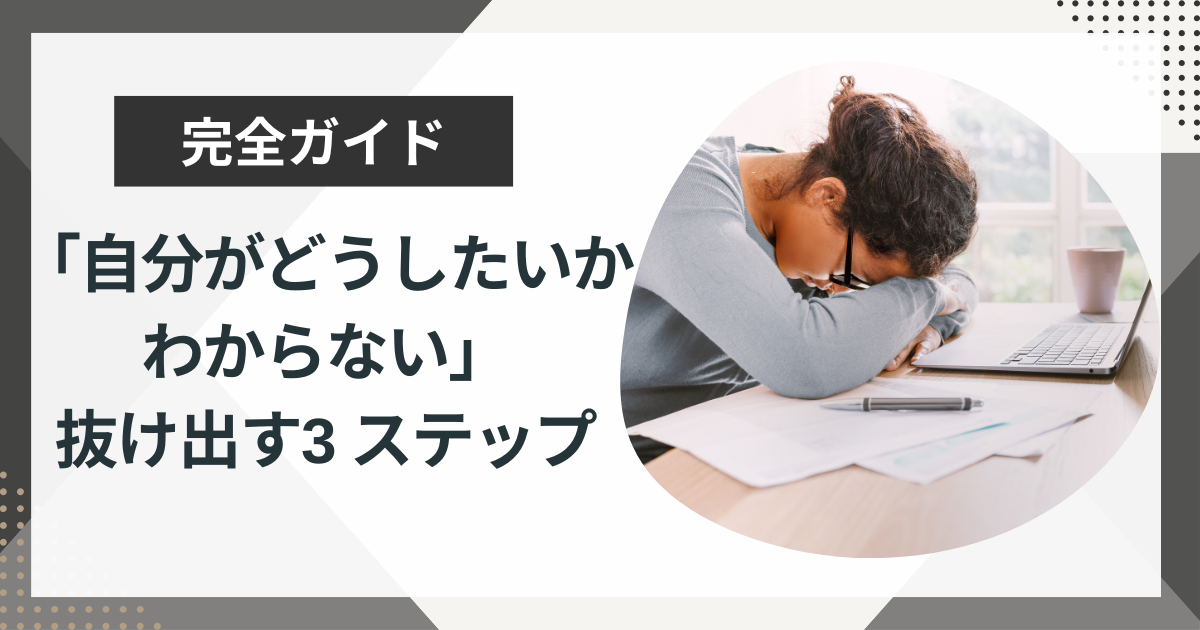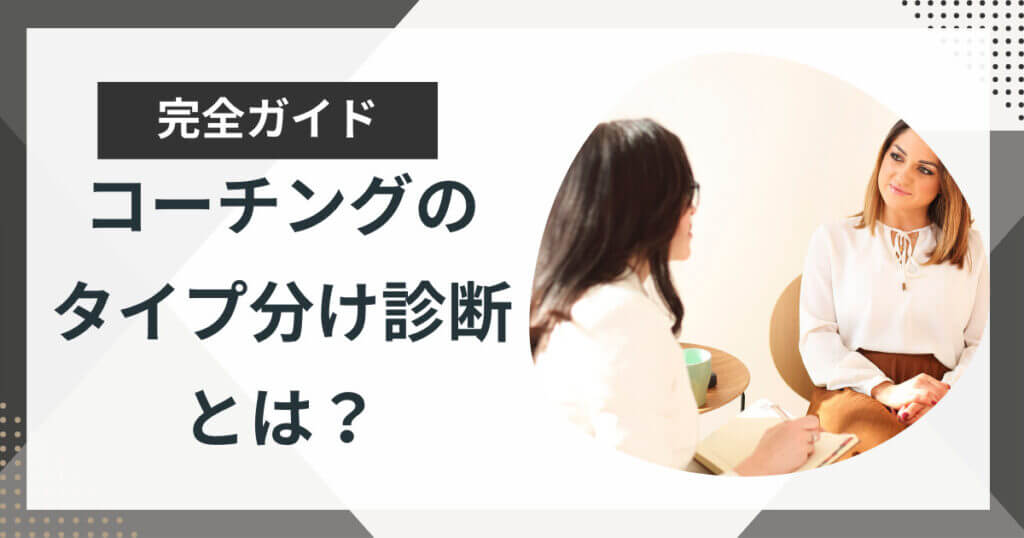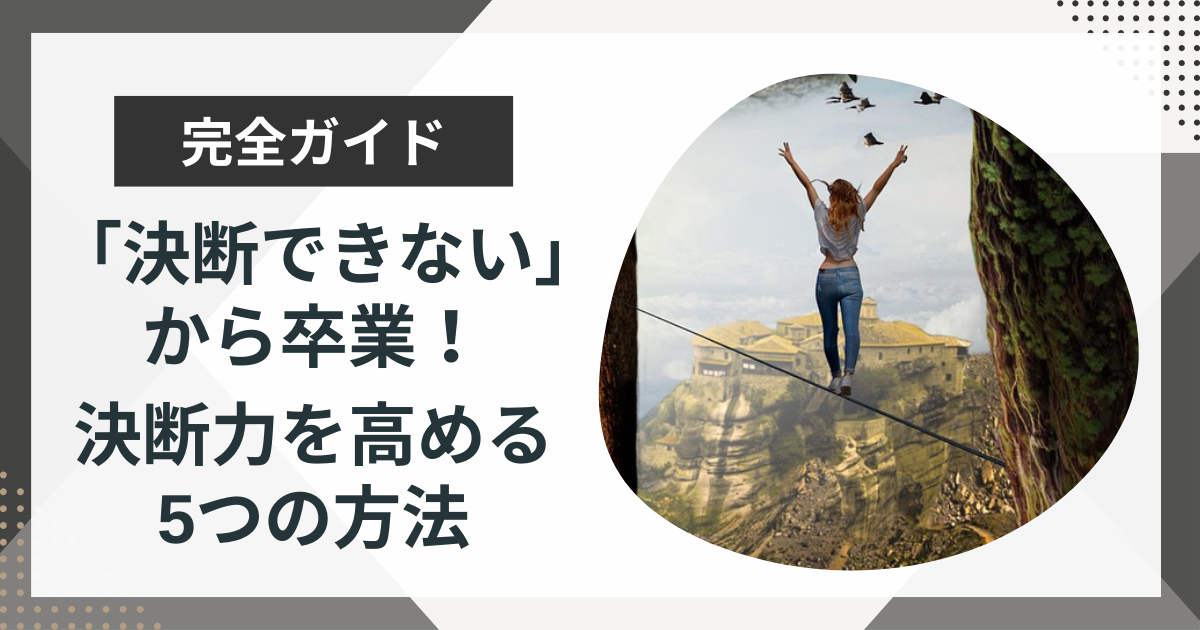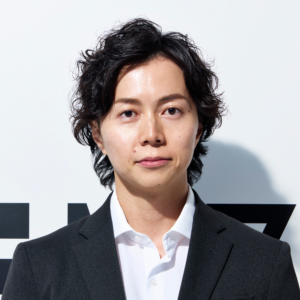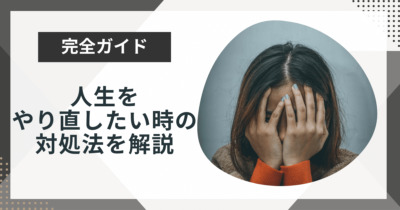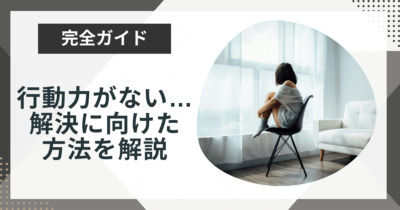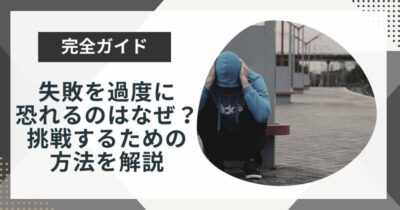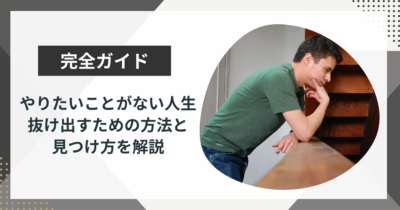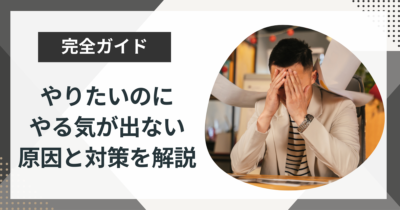「決断できない理由や原因を知りたい」
「日常や仕事において決断力を鍛える方法は?」
この記事では決断できない理由や決断力を鍛える具体策をわかりやすく解説します。
「決断できない自分がいやだ…」
「失敗が怖くて決断できない」
このように、決断できない自分や自分の判断に自信を持てずに悩んでいる人は多いです。
この記事ではコーチングの専門家が、決断できない理由や決断力を高める具体策について徹底解説しています。
この記事を読むと、自信を持って決断できるようになり、不安や迷いなく一歩を踏み出せるようになります。
ゴールを設定することで、やるべきことが明確になり、勝手に決断できるようになります。
ミズカラが無料で提供するGOAL設定ワークでは、ワークに答えるだけで心から欲しい未来が見つかります。
30秒で簡単にもらうことができるので、ぜひ受け取ってみてください。
決断力とは

決断力とは、いくつかの選択肢から1番良い選択を見つけ出し実行に移す能力です。
 ミズカラくん
ミズカラくん決断力は以下の3つの要素から成り立っています。
- 状況を的確に把握する力
- リスクと利益を分析する力
- 選択した決断を実行に移す力
決断力は生まれ持った才能ではなく、努力と実践で身につけられるスキルです。
日常生活やビジネスの場面でも、決断力を磨くとより適切な判断ができるようになります。
自分に自信を持って自分軸で生きられる方法については、以下の記事で詳しく解説しています。
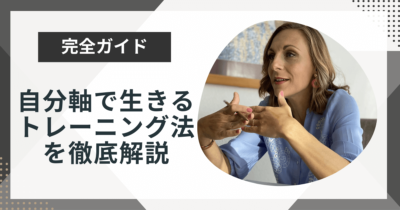
決断力が高い人・低い人の特徴
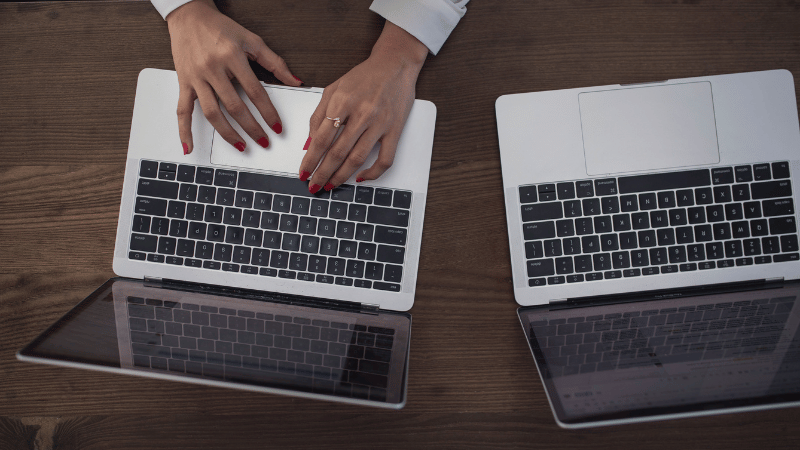
決断力が高い人には以下のような特徴があります。
- チャンスを逃さず掴める
- 問題に素早く対応できる
- 自信を持って選択できる
- 責任感を持って行動できる
一方、決断力が弱い人の特徴は以下のとおりです。
- 機会を逃しやすい
- 問題が大きくなってから対処することになる
- 選択に時間がかかりすぎる
- 自信が持てず迷いが生じやすい
 ミズカラくん
ミズカラくん自分がどうしたいのかわからない状態に…
決断力を高めるためには、決断に対する責任を背負う覚悟を決めることも大切です。
しかし「どんな決断をすれば良いのか」という指針がないと、なかなか行動に移せないものです。
おすすめなのが、ワークシートを使うこと。
簡単・無料・3分で手に入るので、以下からゲットしてみてください。
決断できない5つの理由

どうしても決断できずに歯がゆい思いをするとき、背景にはさまざまな心理的要因が潜んでいます。
- 自信がない
- 失敗して後悔したくない
- 完璧主義
- 判断基準が曖昧
- 決断の影響が予測できない
自信がない
決断できない最大の理由の一つが「自信のなさ」です。
 ミズカラくん
ミズカラくん決断を先送りにしたり、他人の意見に頼りすぎたりしがち。
- 過去の失敗が心の傷になっている
- 周囲から否定的な評価を受けた経験がある
- 「この決断で本当に良いのだろうか」と不安が常にある
- 自分の能力に自信が持てない
自信のなさを克服するためには、以下のようなステップで徐々に自信をつけるとよいでしょう。
- まずは日常的な小さな判断から、意識的に決めていく習慣をつける
- 自分の判断が正しかった経験を書き留めておく
- 周囲からの前向きな評価に目を向ける
例えば「今日のランチ」「週末の予定」を決める。
身近な選択から少しずつ取り組むことで、着実に決断力が高められます。
 ミズカラくん
ミズカラくん日々の小さな決断や経験の積み重ねが自信になります。
失敗して後悔したくない
決断を先送りにする大きな理由の一つが「失敗への恐れ」です。
 ミズカラくん
ミズカラくん例えば、「転職するかどうか」のような重要な決断。
失敗したときの結果が頭をよぎり、仕事を自分で決められないのです。
- 自分の評価が下がってしまう
- お金や時間の無駄になったらどうしよう
- 将来に大きな影響が出るかもしれない
しかし、決断を避け続けると大切なチャンスを逃してしまいます。
 ミズカラくん
ミズカラくん失敗は悪いことばかりではありません。
- より良い判断をするためのヒント
- 自分の強みと弱みの理解
- 次につながる経験や気づき
- 予想外の新しい可能性との出会い
後から振り返ってみると「あの失敗があったから今がある」と感じることも多いものです。
完璧を求めすぎて何も決断できないより、時には思い切って挑戦することで、新しい道が開けることもあります。
 ミズカラくん
ミズカラくん失敗は誰にでもあります。
大切なのは、失敗しても経験を次につなげていく姿勢なのです。
完璧主義
完璧な判断を目指そうとしすぎると、なかなか決断できない思考の罠にはまります。
- すべての情報を集めないと前に進めない
- 細かい部分が気になって全体が見えなくなる
- 「もっといい選択肢があるはず」と考え続ける
- 少しでもリスクがあると決断を迷う
- 失敗が許せない
 ミズカラくん
ミズカラくんしかし、現実の世界に「完璧な判断」は存在しません。
どんな選択にも必ずメリットとデメリットが伴うものです。
完璧主義を克服するには、考え方を少し変えてみましょう。
- 「完璧」ではなく「これくらいで十分」を目指す
- 決断までの期限を明確に決める
- 情報収集に使う時間を制限する
- 失敗しても修正できることを覚えておく
- 経験から学ぶ姿勢を大切にする
大切なのは「完璧な決断」ではなく「今の状況で最善の決断」を目指すことです。
肩の力を抜いて「これくらいで十分」くらいの方が、むしろ良い結果につながることも多いのです。
判断基準が曖昧
判断基準が明確でないと、単純な決断でも迷ってしまいます。
例えば、転職を考える時は、様々な条件が絡みます。
- 給与
- やりがい
- 通勤時間
- 職場の雰囲気
 ミズカラくん
ミズカラくん何を重視すべきか混乱して決断できません。
判断基準を明確にするためには、順を追ってスモールステップで考えてみましょう。
- 自分にとって譲れない条件を決める
- あれば嬉しい条件を挙げる
- 条件に優先順位をつける
判断基準が明確になれば、自信を持って決断できるようになります。
すべての条件を満たす完璧な選択肢を探すのではなく、優先順位の高い条件から順番に検討していくのがコツです。
決断の影響が予測できない
決断の結果が見えないと、前に進むのは難しいものです。
 ミズカラくん
ミズカラくん特に長期的な影響が予測できないと、不安はさらに大きくなります。
- 新しい環境に馴染めるか
- キャリアにプラスになるか
- 将来の昇進の可能性はどうか
- 会社の将来性は安定しているか
上記のような不安に対処するためには、以下のような段階で考えましょう。
- 最悪の事態を想定し、その対策を考える
- できるだけ多くの情報を集める
- 経験者に相談して具体的なイメージを掴む
- 修正できる余地を残しておく
 ミズカラくん
ミズカラくん将来を完璧に予測することは誰にもできません。
ある程度の不確実性は受け入れつつ、自分なりの判断軸を持って決断することが大切です。
決断力をつける方法5つ

決断力は練習と経験を通じて向上させることができます。
- 最悪のケースを想定する
- 判断基準を明確にする
- 小さな選択を意識して行う
- 決断の期限をつける
- ゴール設定を行う
最悪のケースを想定する
最悪のケースを想定すると決断の際の不安が和らぎ、より冷静な判断ができるようになります。
- 最悪のケースを考える
- 確率を考える
- 対策を検討する
- 他の可能性を検討する
段階を踏んで考えることで、決断に伴うリスクを客観的に評価でき、過度な不安を軽減できます。
また、最悪の事態に備えることで、安心感を持てるのもメリット。
 ミズカラくん
ミズカラくん自信を持って決断できるようになります。
判断基準を明確にする
判断基準を明確にすることで迷いが減り、自信を持って決断できるようになります。
 ミズカラくん
ミズカラくん以下の手順で考えてみましょう。
- 何を決めたいのかを明確にする
- 大切な要素を書き出す
- どの要素を特に重視するか決める
- 具体的な評価方法を決める
例えば、新しい仕事を選ぶ際の評価については、以下の要素で考えるとよいでしょう。
- 給与はどうか
- 成長できるか
- 新しいスキルを学べるか
- 残業は多いか
- 休みは取れるか
上記のように整理して考えると、感情だけに頼らず冷静に判断できるようになります。
 ミズカラくん
ミズカラくんまた、後から「なぜこの決断をしたのか」を説明することもできます。
小さな選択を意識して行う
普段の生活の中で「小さな選択」を意識すると、決断力は確実に高まっていきます。
以下のような身近な場面から、意識的に決断する習慣をつけてみましょう。
- 朝食のメニューを決める
- 服装を選ぶ
- 休日の過ごし方を決める
- 新しいレストランを選ぶ
日常の小さな決断を積み重ねることで、決断への恐れや不安が徐々に減っていきます。
 ミズカラくん
ミズカラくん仕事や人生の重要な場面でも、自信を持って決断できるようになります。
決断の期限をつける
決断に期限をつけることで、前に進むことができます。
 ミズカラくん
ミズカラくん考えすぎて行動できない状態から抜け出せるのです。
- 必要な決断を書き出す
- 一つ一つ期限を決める
- 期限を目に見える形にする
上記のように期限を決めると、計画的かつ現実的な判断と決断ができるようになります。
ゴール設定を行う
ゴールを明確にすると迷いが減り、自信を持って決断できるようになります。
- 大きな目標を描く
- 中間目標を立てる
- 近い目標を設定する
- いつまでに達成するか決める
目標を段階的に設定することで、ブレない選択ができるようになったりします。
しかし、「どんな目標を立てたらいいかわからない」と迷う人も多いですしょう。
 ミズカラくん
ミズカラくんそこでおすすめなのが、ワークシート。
簡単・無料・3分で手に入るので、以下からゲットしてみてください。
決断できない時の2つの対処法
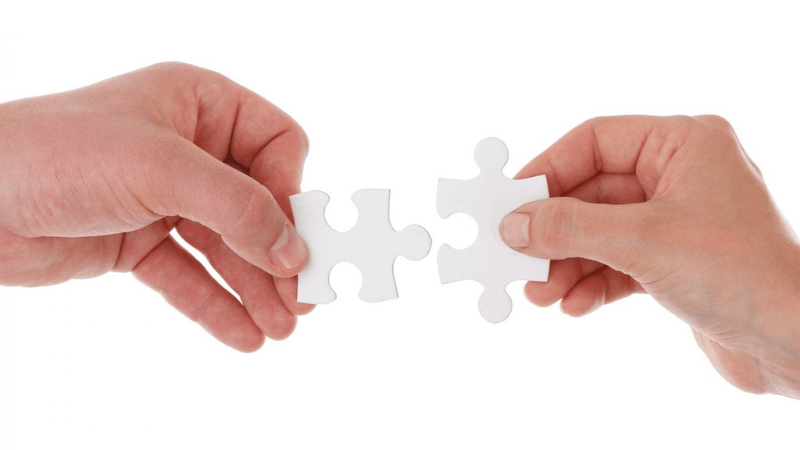
決断力を高める努力をしていても、決断に迷うことがあります。
ここでは決断に迷った時に役立つ2つの対処法を紹介します。
- 優先事項を基準にする
- 「完璧」より「70%」を目指す
優先事項を基準にする
優先事項をしっかり決めることで、選択に迷う時間を大幅に減らすことができます。
 ミズカラくん
ミズカラくん以下の手順で優先順位を明確にしましょう。
- 価値観を見つめ直す
- 決断との関係を考える
- 一番大切なことを基準に決める
例えば、転職の際の優先順位を次のように考えます。
- キャリアの成長機会
- 収入の安定性
- 仕事と生活のバランス
上記のように優先順位を明確にしておけば、迷いが生じても自分の軸に立ち返って決められます。
「完璧」より「70%」を目指す
「完璧な選択」にこだわって、なかなか決断できないときは「70%ルール」の活用がおすすめです。
70%ルールとは、必要な情報が70%程度そろっていれば、前に進もうという考え方です。
- 「70%」の基準を決める
- 各選択肢を比べる
- 基準を満たす中から選ぶ
- 後から調整できることを考える
以上のように、完璧な選択を目指すのではなく「70%くらいの良い選択」を見つければよしとしましょう。
どんな選択にも良い面と悪い面があるのは当たり前です。
 ミズカラくん
ミズカラくん今の状況で一番マシな選択をして、必要なら後で修正すれば十分です。
決断できない時の対処法について、以下の動画も参考にご覧ください。
決断力をつける3つのメリット
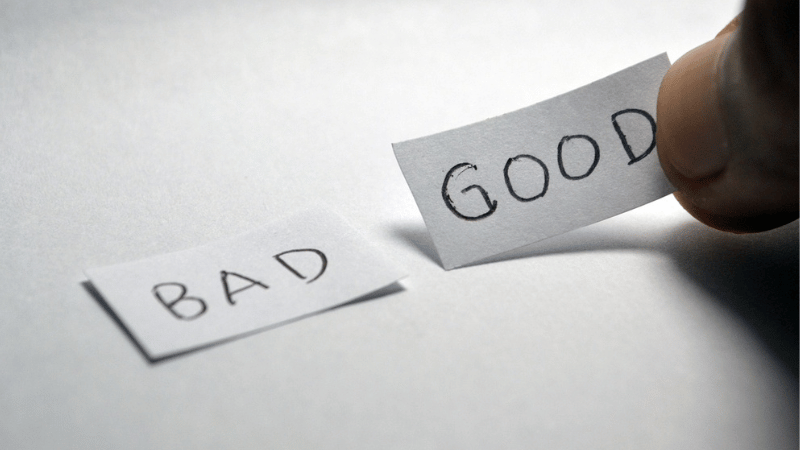
決断力を高める3つのメリットについて詳しく説明します。
- 成功する可能性が高まる
- 人生の後悔が減る
- 人生が充実する
成功する可能性が高まる
 ミズカラくん
ミズカラくん決断力が上がると、成功につながりやすくなります。
- チャンスを掴めるから
- リスクに強くなるから
- 問題を素早く解決できるから
- ブレない行動ができるから
上記のように、決断力を磨けば仕事では成果が出やすくなり、私生活では充実感が高まります。
また、失敗しても早めに気付いて軌道修正できるので、最終的な成功率を確実に上げられます。
人生の後悔が減る
「やった後悔」より「やらなかった後悔」の方が後に大きく残ります。
決断力を高めることで、やらなかった後悔を減らし、人生の後悔を減らすことができます。
- チャンスを活かせるから
- 結果を受け入れやすいから
- 挑戦する勇気が出るから
- 経験を次に活かせるから
 ミズカラくん
ミズカラくん人生の最後に後悔するのは「やらなかったこと」です。
たとえ失敗しても「自分で決めて挑戦した」という事実は、大きな自信になります。
人生が充実する
決断力を高めることで、人生はより豊かで充実したものになります。
- 自分で人生を作っている実感があるから
- 心にゆとりが生まれる から
- 大切なことに時間を使えるから
- 周りとの関係が良くなる から
 ミズカラくん
ミズカラくん決断力を磨けば人生をより自分らしく生きられます。
自分の選択に責任を持ち、前向きに進むことで、充実した毎日を送ることができるのです。
「決断できない」人からよくある質問
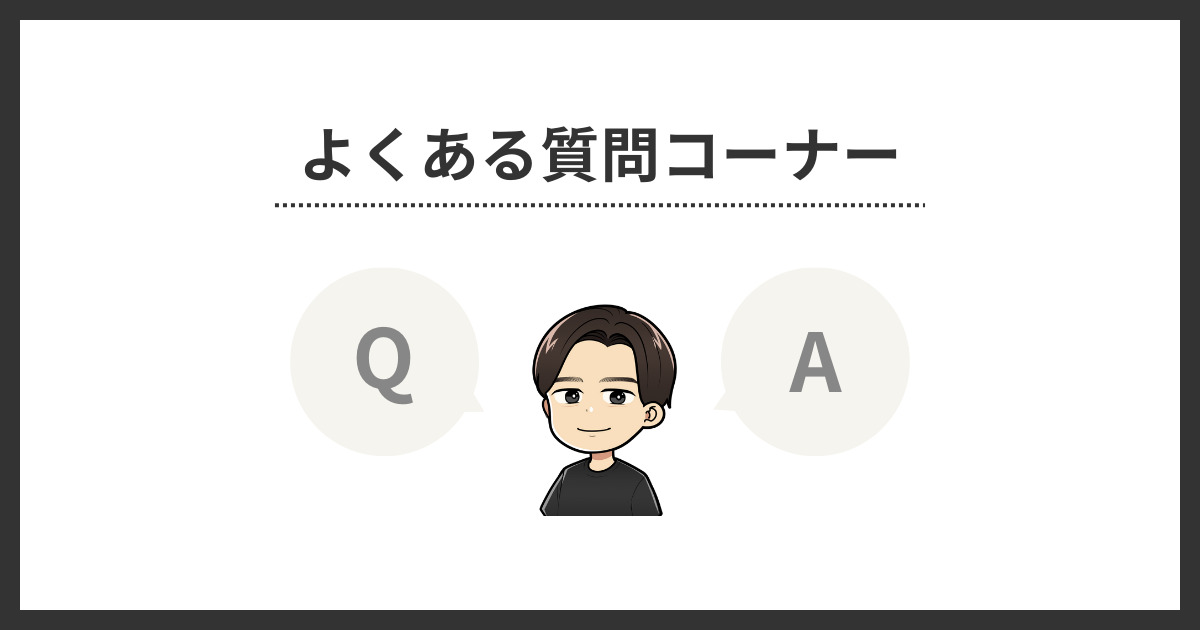
「決断できない」人からよくある質問は以下のとおりです。
- 決断力をつける方法はありますか?
- 決断が遅い人の特徴は?
- 決断が遅い人の特徴は?
- 物事を決断できないのは病気ですか?
- 決断力をつける方法はありますか?
-
決断力は生まれつきのものではなく、努力や練習を通じて徐々に身に付くスキルです。
決断力をつける方法- 最悪のケースを想定する
- 判断基準を明確にする
- 小さな選択を意識して行う
- 決断の期限をつける
- ゴール設定を行う
小さな決断から始めて、徐々に重要な決断をすることで、決断力は着実に向上していきます。
- 決断が遅い人の特徴は?
-
決断が遅い人には、次のような特徴が見られます。
決断が遅い人の特徴- 情報収集に時間をかけすぎる
- 失敗への恐怖心が強い
- 目標や価値観が曖昧
- 優柔不断な性格
- 完璧主義
上記の特徴が当てはまる場合は、自分自身の行動パターンを見直してみましょう。
- 物事を決断できないのは病気ですか?
-
物事を決断できないこと自体は病気ではありません。
しかし、背景に心理的・精神的な問題が影響している場合があります。
以下の場合には専門家への相談も検討してみましょう。
専門家に相談したいケース- 過度な不安症や恐怖感
- 強迫性障害(OCD)
- ADHD(注意欠陥・多動性障害)
まとめ:「決断できない」心理的な理由5つと決断力を高める5つの具体策

決断力は、意識的に高めることができるスキルです。
この記事で紹介した対処法を活用して、スムーズな決断ができるよう心がけましょう。
- 最悪のケースを想定する
- 判断基準を明確にする
- 小さな選択を意識して行う
- 決断の期限をつける
- ゴール設定を行う
しかし「一人では難しい」「具体的な方法がわからない」という人は、キャリアコーチングの活用がおすすめです。
キャリアコーチングでは、プロがあなたの悩みに寄り添いながら、的確なアドバイスをしてくれます。
決断の仕方から具体的な行動計画まで、一緒に考えていけるので安心です。
 ミズカラくん
ミズカラくん以下のような方は、特にキャリアコーチングの活用をおすすめします。
- 重要な決断を控えている
- 決断に自信が持てない
- 判断基準を明確にしたい
- 効率的に決断力を高めたい
キャリアコーチングについて、より詳しく知りたい方は以下の動画もご覧ください。